|
|
「演奏のマニュアル」
<4.演奏上の注意>
はじめに
<2.演奏とは?><3.奏法の知識>と進んできましたが、次の<5.音楽の解釈>に進んで行く為に、前もって演奏上注意しておかなくては成らない事が有ります。
もちろんそれは音楽の解釈だけの問題ではなく、演奏する上での注意すべき事でも有ります。
今までの「音楽のマニュアル」などの著書でも述べてきた物もあるので、重複する所はお許し下さい。
「普通の感覚」のテンポ
始めての楽譜を見た時に、最初に気になり見る所はテンポの指示かもしれませんが、私は、見ません。
まずは音符を読んでから見る事にしています。
しばらく読んで行くうちに、その旋律感が頭に残ってくる。そうすると自然にその音楽が本来持っているテンポが解って来るのです。それからはじめて速度標語を見る。
メトロノーム数が有れば、今自分の頭の中で鳴っている音楽とのテンポの違いはハッキリとする。もちろん、遅い場合も、速い場合も、全く同じ場合も有る。そこが作曲家との「対話」であると考えているのです。
「彼はこの旋律を「普通の感覚」より遅く(速く)する事で、何かを訴えようとしているのだ」とか、何かを言う前にその素材として「これを使う」と、まず「普通の感覚」の形で提示している、などだ。
後の章で、「普通の感覚」について詳しく述べますが、今はこのまま受け取って下さい。
旋律の流れ
旋律が有ると、そこには音楽の「流れ」が有る。それは誰でもが同じ「流れ」を思っているかもしれないし、みんな違っているかもしれない。つまり、わたしにとって「普通の感覚」であってもそれが、他人の「普通の感覚」であるかは判らないのである。これは作曲家との関係においても同じ事だ。
速度標語で、「Moderato」 という語がある。日本語訳では、「中庸に、適度に」(岩波小事典 音楽 第2版 山根銀二編 岩波書店)とある。英語の音楽辞書では、「Neither fast nor slow」(Belwin Pocket Dicttionaryof Music by WILLIAM LEE Belwin. Inc.)大きな辞書を参考にしなかったが、それはあまり専門的な見解より、一般的な認識としての知識を知るためだ。
このどちらでも良いが、とても「曖昧」だ。「流れ」を表す言葉だからだ。
中にはメトロノームで幾らと書かれた物もあるが、一般的ではないし、大概は外れていると誰もが思っている。
この点が「注意すべき点」として取り上げた、理由である。
実に「曖昧」であり、実に「本質論」なのである。
「普通の感覚で」
我々の感覚は、測れるものと、測れない物がある。
物の長さは測れる、音程も測れる。時間の感覚は測れるが、流れの速さは測れない。測れてもかなり「曖昧」だ。
この測れる測れないは、客観的な「量」と「感覚」がどの程度一致するかの問題と思う。
指先で数ミクロンの違いが判る人がいるそうだ。感覚で1秒を正確に言い当てる人も少なくない。しかしこれらの感覚は、「普通の感覚」ではないのだ。
それらの人が、「これは狂っている」と言うのは、我々には「どうでも良い事」なのだ。もちろんその道では必要だから磨いた感覚で、決して無意味だなんて全く思っているので無く、むしろ大変尊敬する事で有る。
いま「どうでも良い事」と言うのは、音楽のような感情を問題にする分野での事である。
しかしこの分野でも、メトロノーム数1つも狂わない事を自慢にしている人もいる。それもそれで素晴らしい技術であるが、軽蔑するわけではないが尊敬の対象ではないし、自分自身でも身に付けようなどとは思わない。
それよりも大切な事は、「普通の感覚」の方だ。
では、前の「Moderato」の速さは一体何なのであろうか? 「普通の感覚」で、だ。
「Allegro Moderato」と言うのがある。「普通の速い感覚」なのである。速くて「普通の感覚」と言い換えても良いだろう。なんとなく判ってきた気がする。
メトロノーム数(以後はM.M.と記す事とする)は一般的ではないと言ったが、M.M.72は、おおよそ安静時の脈拍数であるが、もっと遅い人も速い人もいる。遅い人は、この数字の速さを速いと思うであろうか? そんな事は無い。
私は若い時から通常の脈拍が、M.M.90以上あったが、M.M.72を遅いと思った事は無い。
しかし多くの人は、M.M.60を遅いと思う。この速さは、1秒だ。時計の秒針と一緒に数えると、微妙に遅い。
この二倍のM.M.120は、速いと思う。この2/3である、M.M.90 は微妙に速い。やはりM.M.72 は、「そこそこ」中庸と言えるかもしれない。
テンポの流れは、「誰もが同じ「流れ」を思っているかもしれないし、みんな違っているかもしれない」と言ったが、どうもおおよそ同じ様な感覚を持っていそうだ。
ベートーベンのテンポ
メトロノーム数の問題は、今後も論議を呼ぶだろう事は判っている。何故ならベートーベンのメトロノーム数の問題があるからだ。
彼のM.M.の数は、「速い」。
それでもこの通りにしなければならないとの主張は多い。またしている演奏家も沢山いる。しかし、やはり「速すぎる」と思う。
それでは、ベートーベンの記述を無視するのかと言う問題に突き当たる。
私は、今まで主張してきた様に、演奏とは作曲家の意思に従って代弁する事だとの姿勢で話しを進めてきた。それに変わりは無い。でもどうしても彼の速度は、速いのだ。
私の仮説は、2つ有る。
1つは、メトロノームに刻まれた目盛がずれていた。
もう1つは、メトロノームの数字の基準になった時計の精度が少し遅かった。 以上だ。
どちらにしてもこの数字は間違っている。と言うのが私の結論だ。
この事についての審議は、別の機会に委ねたい。今は、何故このような結論を導いたかを判って頂きたいので有る。
この章の最初に述べた思考順序で、ベートーベンの作品を見ていくと、この様な結論に達するのだ。
まずは音符を読み、その「普通の感覚」で「流れ」を感じて見る。そうすると大概は記述より遅いのだ。
そこに何らかの意図は考えられない。何故なら、通常ソナタ形式を取っているなら、最初は提示から始まる。いきなり展開させる事はめったに無い。「運命」でも「田園」でも最初は提示だろう。とても印象的では有るが、その印象は「普通の感覚」としてだ。
いきなりその作曲家独自のテンポ感で始めたとしても、それに聴衆はついて行けない。いきなり怒り出した人が目の前に現れたような物だ。印象的では有るが論理的ではない。
1種のショック技法としては考えられるが、頻繁には使えない。ひょっとすると「運命」では使ったのかもしれない。「突然のノック」ならそれも有るだろう。しかし聴衆は「驚いた」だけでそこにそれ以上の思考は働かない。その後でだんだん説明して行く事にはなる。
例外的な技法としたい。
流れ
話を「流れ」に戻そう。
「運命」と「田園」の始まりの旋律を思い比べて下さい。
「運命」の冒頭は、「流れ」は無い。一瞬の出来事だ。この後でも詳しく解釈をする「エグモント序曲」の冒頭もそうだ。
しかし、「田園」の始まりには、「ほのぼの」とした「流れ」が有る。
もちろん「運命」の一瞬の音をその様な「流れ」と言ってしまっても、それに異論は無いが、今論じるのは「普通の感覚」での「流れ」だ。
「田園」の流れは、この流れの感覚だけで十分に「のどか」な田園を連想させる。「普通の感覚」だ。その流れは、一定ではない。遅くなったり速くなったりを繰り返す。しかし楽譜の上では、拍子もテンポも変更は無い。
しばらくすると、根底に一定の流れがだんだんとハッキリとしてくる。次の音形だ。(譜例2)
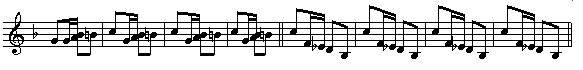
譜例2 「田園」より
かなりのスピード感が有るこの音形が、だんだんとハッキリして延々と続いて行く。
延々と同じ流れ(リズム)が続くのは、「普通の感覚」ではない。特別な物で有る。想像を働かせば、「馬車の音」に感じる。
その馬車に乗ったベートーベンが、田園風景を、「のどか」な気分や、「小川のせせらぎ」の流れ、「鳥の声」などで、この根底の馬車の流れと「対比的」な流れでながめている。
同じ流れでは、混在して埋没してしまうだろう。つまり、同じ拍子で同じ速度に書かれていても、旋律には、「それぞれ別の流れ」を持っているので有る。
これが最も巧みであるのは、モーツアルトかもしれない。
特にオペラでは、色々なキャラクターがそれぞれの思惑で演じているのだから、同じ旋律感(流れ)ではない。だから、それぞれが独自の流れを持って絡み合う様に書かれている。
それがすべて違った拍子やテンポで書かれては一緒に演奏は出来ない。同じ拍子の中で絶妙にアンサンブルするのである。
すなわち、同じテンポに書かれていても、それぞれの旋律によって「流れ」を違うように考えなくては成らないのだ。
ゆえに今、「拍子」「テンポ」「流れ」と区別して使っている。
それぞれを定義すれば、
拍子 :根底に流れる共通の流れの単位。
テンポ :ビートとも言って良いかもしれない。拍単位でのスピードの設定。
流れ :音楽の本来持っているスピード感。
この「拍子」と「テンポ」は物で言えば「目盛」に相当する物で、表面的には見たり感じたり出来ない。つまり聞えない、いや聞えてはいけない物だ。
インテンポ
もう一点「テンポ」に関しての注意すべき「インテンポ」について述べておく必要が在る。
テンポ感について述べてきたが、「曖昧な物」で在ると述べた。しかし演奏する人にとって「曖昧」では困る。
後で述べる「音程」は、人間の感覚は想像以上に敏感であり、記憶もかなりハッキリ出来るが、この「テンポ」は、感覚はかなり不確定だ。
演奏すれば、誰でもが細かい音形は早く、粗い音形は遅く成ってしまう。これは、細かい音形だと「速い動きだ」、粗いと「ユックリした流れだ」と思っている感情が、演奏に現われてしまうからだ。これは本来の「作曲家の意図」にはない事だ。
ゆえにその様な感情が直接現われないようにしなくてはならない。それには訓練しかない。
どのような場合でも一定のテンポを維持できる能力を付けておく必要が有る。インテンポの技術である。
音楽は「何時でもインテンポでなくてはならない」と思っている人もいるが、それは正しく無い。必要な時には出来る技術が要るのだ。
音楽の中で「インテンポ」が必要かどうかは、その度に考えて行く事である。それも機械的にインテンポが必要というよりも、その様に聴衆が感じる様にする事が目的である。
その為にも、機械的「インテンポ」が出来る能力は持っておかなくては、判断がつかない。
心地よい「インテンポ」は、「1/fゆらぎ」を持っているといわれる。ここではその詳しい説明は省くが、若干の「ゆらぎ」がある事は感覚的にも理解できるであろう。それを意識的に出来る事が大切なのである。「きもちのいい」事なので「気持ち良く演奏さえすれば良い」との結論は、自分の感覚と他人とが「シンクロ」しているとの「錯覚」でしかない。
聴く人は、そのパッセージが難しいとか弾き易いとかは、全く音楽の本質とは関係のない事だ。その様な自分自身の技術的難点の感情や都合を、音楽の表情に置き換える事は許されない。
それこそ「練習をしなさい!」です。
何の感情も無く、「普通にしゃべっている」ように演奏「できる事」が、演奏をする大前提です。
それが客観的に出来ていることを確認するのに、メトロノームのような機械の力を借りる事は良い事です。
テクニックを磨く
テクニックを磨く最も賢明な方法は、最も単純なモデルを設定して、それに極力近づけるようにする事です。
どんなにやっても、決して行き着きません。それはやればやるほどに、その単純なモデルのディティールが解って来るので、益々目標が高くなるからです。 それぞれのレヴェルに応じた有効な練習です。
ただしその人物の探求心も現われますので、「適当な」事で済ましてしまう人には、強く厳しくそれを指導してくれる先生がいるでしょう。
再度述べますが、テンポ感覚は「曖昧」ですので、この能力は日夜訓練が必要です。
一度出来たからと思って、訓練を怠ると途端に「わがまま」な自分勝手なテンポでやってしまう事に成ってしまいます。それに気が付けば良いのですが、大概は自分自身は「気持ちが良い」ので、自分自身はしっかりとした「テンポ」だと思ってしまうことです。
廻りの人は「なんとわがままな人だ」としか思わないのです。気をつけましょう。
①テンポの最後で、「拍子」は聞こえない物と述べた事に、多くの人は疑問に思うでしょう。
2拍子3拍子は聞いて判る、行進曲は2拍子、ワルツは3拍子で当たり前だ。
では「田園」の冒頭は何拍子ですか?2楽章は?
楽譜を見た事がある人には、何も難しくは無いでしょう。
しかし、楽譜を見ずに正確に答えられる人は、そんなにいないと思います。
答えは1楽章は2/4拍子、2楽章は12/8拍子です。
それぞれを、4/4や2楽章を6/8と間違った人は、かなり答えに近いでしょう。
しかしそんな事は判らなくても音楽を聴く事は出来ますし、そんな事を考えて聴く人は、ほとんどいないでしょう。
でも1楽章と2楽章の音楽の基本的流れが、なんとなく違う事は判ると思います。それは、「拍子」が聞えたのではないのです。楽典的に言えば、1楽章が単純拍子で、2楽章が複合拍子なので、その拍子感の違いが判ったのでしょう。
単純拍子は「1-2、1-2、」、複合拍子は「1~ト、2~ト」のスウィングの「リズム」を持っています。
この「リズム」がここのテーマです。
リズムとは?
さて、何が違うのでしょう?
単純拍子の各拍は「1:1」に分けられ、複合拍子は「2:1」に分ける事ができます。
単純拍子は直線的、複合拍子は「振り子」のような曲線的、とでも言いましょうか。
この様な言葉での説明は大変に「まどろこしい」のですが、これでなんとなく解って頂けると思います。
もしも同じテンポ(仮にM.M.60)で、どちらも1拍づつの音が在るとしましょう。どちらも、1秒音がしています。その違いは分かるのでしょうか?
完全に判ります。その違いは、敢えて言葉で言えば、直線的な「変化」と、放物線的「変化」の違いです。
左右に直線運動するのと、振り子運動するのとの違いでしたら、想像できるでしょう。それが音の表情として現われます。
これが「リズム」の違いです。いやそれは、「リズム」が違うのではなく「拍子」の違いだとおっしゃるかも知れません。それはそれで間違いでは在りません。基本的に、直線運動の「リズム」を基本にしている拍子を単純拍子、放物線運動の「リズム」を基本にしているのが複合拍子というのですから。
これで、2/4と6/8の拍子の違いが判ったと思います。 実は基本の「リズム」が違うのです。
普通「リズム」とは、前出の辞書(岩波小事典 音楽 第2版 山根銀二編 岩波書店)では、「音の動きが形作る時間的な秩序の事。」別の良い方で、「音と音との時間的関係によって作られている。」これでは十分ではないので、さらに「リズムという言葉には動き、流れ具合と言った一層動的で広い意味合いが含まれる。」と、まやこの後に延々と説明が成されているのです。
この説明の始めの方に在る、「時間的秩序」の考えは、よく親が子供に「リズム守って生活をしなさい」などと規則正しい生活を指して使う事が在る。繰り返し同じパターンを持つ物を、「リズム」正しく、と表現する。
またジャズなどポップスでは、「のり」の良い「リズム」等と使い、動きが激しい様を言う。
「リズム」の概念
「リズム」とはこの様な意味の用語ではあるが、我々音楽を演奏する者が認識すべき「リズム」の概念は、あくまで「動き」という一言に集約すべきであろう。
すなわち、1つの音の持っている表情が、どのような「動き」を持っているかで有る。
激しくポップするのも「リズム」、動きの無いのも「リズム」、1度だけでも「リズム」がある、もちろん譜例1のような連続した一定の動きの繰り返しの場合も「リズム」の表現だ。
重要な事
最も注意すべき重要な点は、音にはいつもなんらかの「動き」が無くては成らないし、そこが色々な表現をする所で有る。それを「リズム」が有ると言う事だ。
もし数学的に言うのであれば、音の変化率が「リズム」だ。それを微分して書かれたのが、音符のリズムだ。
演奏はそれを見て、積分する作業だ。
前項にもこの問題を少し述べたが、まだ説明しておかなければ成らない注意点が有ります。
まず頭にいれて頂きたいのは、「絶対的に正しい音程は存在し無い」と言うことです。
正確には、絶対的に正しい「音程」はあるが、絶対的に正しい「ピッチ」は無いと言う事です。
「音程」とは本来この字の通りに、音と音との隔たり、距離の事である。
この意味で使う限り正しい「音程」は在るし、それを知っておかなくては成らない。「音と音の関係」といっても良いかもしれない。
しかし、「音程」を「ピッチ」の意味で使う(この方が多いかもしれない)のであれば、絶対的なものは無い。つまり、音の高さである「ピッチ」は、相対的な音の関係つまり「音程」で決まるのである。我々はこの、音の関係の「音程」感覚を養わなくてはならないのだ。
それは難しくない。何故なら、この感覚は「普通の感覚」で判断するからである。
つまり、聴く側にとっての「心地よい」音の関係なのである。これは、①テンポの感覚の場合とは違い、それが日によって又気分によっては変わらない。
演奏する側も、もちろん演奏技術が未熟でコントロールできない場合は論外だが、しっかりとした技術(音楽的能力でなく)を持った演奏家にとっても「心地よい」音の関係なのである。
重ねて言うが、「音の関係の音程」は絶対的なもので有る。
絶対音感
今述べ様とする音の関係の「音程」と、先ほど説明した音の高さの「ピッチ」を取り違えると、絶対音感の論議が食い違う事と成る。
ある特定の音を音名で区別できる能力を、絶対音感といっている。作曲家にはこれほど役に立つ有用な能力は無いであろう。
自分の頭にある音をすぐに楽譜に置き換える事が出来るからだ。
しかし、今述べている演奏家にとってこの能力は、場合によっては「邪魔に成る」場合が有る。
それは、この能力が完全に一定の高さだけを音名にするのであれば問題は無いが、四捨五入の様に、ある音をその上か下の決まった音名の範疇へ入れてしまわなければ成らない。ようするにデジタル化だ。
ここには、「平均律」しか存在しない。「純正律」はすべて「平均律」の音へ変換されてしまうのである。
作曲家にとっては「便利な物」、演奏家には「邪魔な物」なのだ。
音楽家は音の専門家であるので、音に対しての注意力、特に美しい音への集中力は高いはずだ。その音楽家が、音の自然な「音程」関係を無視して、「おおよそ」の音の関係で満足してはいないはずだ。
それこそがこの項での取り扱う、「音程」の問題で有る。
音楽においての心地よい「音」を、多くの一般の人は「ハーモニー」というでしょう。今そこから話を始めます。
ハーモニー
良い演奏=美しい演奏=ハーモニーが整っている=音程(ピッチ)が正しい
この様な方程式は、結論を言えば間違っています。後の2つは、少し言い変えれば正しくなるでしょう。
ハーモニーが整っている=音程(音の関係)が正しい
その前の方程式は、「美しい演奏」には「ハーモニーが整っている」事は含まれる。しいて直せば、美しい演奏=最後のハーモニーが整っている
最初の、良い演奏=美しい演奏 はあまりに深く、問題にするにはこの中では論じきれない問題の様に思うので、また別の機会を持って論じたいと思っています。
つまり、音楽は音の関係が、「心地よかったり、悪かったり」を繰り返し、最後に整った響にたどり着きたいのです。それをポピュラーの世界では、「コード進行」と言っています。
「進行」と言う言葉が付いているのです。和声学でも習った方は経験が在ると思いますが、「和音の進行」を先生に注意されます。
その時は、「何と堅苦しく型にはめなければならないのか」と思い、和声の勉強が嫌いに成ってしまう事が多いのですが、実はそこが本来の和声の重要な点なのです。
それがあまりクローズアップされていないのは原因があります。
和声学を教授する人はほとんどが作曲家です。彼等はこの和声の進行を何か新しい物は無いかと、日ごろから探し続けているのです。
目新しい「和音」はもうとっくに出尽くした感があります。新しい進行は、コード進行の世界では、特許にしていると言う話すらあります。その意味では音楽理論界では、大変に研究の進んだ分野です。
前にも言いましたが、演奏の分野では、これを楽曲分析の最重要ツールとしてきました。それゆえにどのような音の重なりも、何かのハーモニニーであると分析できてしまいます。それは便利なものです。
しかし、そこでこの「進行」の問題を置き忘れてしまうのです。
確かにハーモニーは「面白い響」で、興味を引きます。しかし何度も申し上げている事ですが、いくら興味深い「面白い響」であっても、それが単独で鳴る限りは、何ら「意味ある響」ではないのです。
やはり「響の変化」が意味を作るのです。
そろそろ結論です。
ハーモニーは結果です。意味ある音の動きが、ある時は美しく、ある時は「ぶつかり合う」変化が、音楽です。その時々の切り口が「ハーモニー」です。
この変化を取り扱う学問が、「対位法」です。
対位法
音楽と言えばハーモニーと言うように、ハーモニーが音楽の最重要学問が和声学(ハーモニー理論、またはコード進行)の様にされて来ましたが、西欧での音楽の発展の中ではそれよりも先にこの「対位法」があります。
有名な作曲家の伝記などでも、見とめられたり何かの御褒美で「ローマへ対位法の勉強に行った」との記述は度々見かけます。
「和声学」ほどの明瞭な理論で無いだけに解り難く、特に日本では音楽大学の授業でもたまにしか開講されないで、それも作曲家の生徒の為にだけの場合が多いのが現状です。
簡単に言えば、「複数旋律の絡み合いの技術」と言っても良いでしょう。演奏家にはとても必要な学問です。
前にハーモニーでの「変化」の問題点を取り上げた事はお解り頂いたと思いますが、3つ以上の音が同時に演奏されれば、御互いの音同士が、「協和」したり「不協和」したりする事は想像できます。
でも、2つの音ではこの様になるかどうかは疑問に思うでしょう。
特に和声学をまず考えてしまう人には、すべて「協和」している様に思うかもしれません。
それは「和声学」が先ほど述べた様に分析学として有用な点の証明でしょう。ようするに「理論的」に理解し易い為です。
しかし2つの音だけでも「協和」したり「不協和」したりする事があり、想像もできます。それが音楽の意味や感情の表現となっていることを理解していただきたいと思います。
<3. 奏法の知識> 2、音の表情 B、イントネーション イ、音程 の項で説明した事を少し思い出して頂きたいと思います。自然倍音の関係からすべて協和する音律を「純正律」と言うのだと申しました。
しかしすべて「協和」するのは、主音との関係なのです。それぞれの音同士がすべて「協和」はしません。むしろしない方が多いかもしれませんし、その「不協和」した時は大変にひどい音がします。ヴォルフトーンと言って、「狼の唸り声」に例えられたりしています。
それに比べて「平均律」は「協和」も「そこそこ」しかしませんが、「不協和」もそこまでひどい音がしません。それが好まれて使われる最大の理由でしょう。
その「平均律」で演奏しますと、この2つの旋律の関係はどの様になるでしょう?
「そこそこ」の関係しか表せない事は、容易に想像できると思います。
それがハッキリ表現できなければ、このそれぞれの旋律の絡み合いから生まれる感情や意味は、表現出来ていない事と成ります。実際にはそれほどでもないのですが、その事は後の旋律のところで説明します。
では「純正律」であれば良いのでしょうか? 今述べた様に、それだけでも上手くは行きません。
もし新たな「すべてが協和する」音律が発明されたとしましょう。でも今度はすべてが「協和」してしまうので、それぞれの独自性は乏しくなります。
コーラスで、「純正律」こそが唯一正しい音律だと信じている人達がいますが、この様な音楽を目指している事と同じです。
確かにハーモニーが整って「美しく」響きますが、そこに主張や意味は聞えません。「美しく」響く事が主張だと言われるでしょうが、それは存在していても主張かどうかの判断は、聴く人の内面でのことです。演奏で表現したとは言えません。景色や物の様にそこに存在するだけです。それも芸術では?と言う議論は、今はしません。
少なくとも今まで作曲された作品は、ほとんどが変化を主張しようとしているのです。その演奏をいかにするかの「演奏のマニュアル」を今書いているのです。
すなわち、「平均律」も「純正律」も完全では無いと言う事です。
結果、我々はいつも「最もふさわしい」音の関係を考えながら演奏しなくてはなら無いと言う事です。
それを考えるには、旋律において「音程」を考えるのが解決の方法であり、特に単旋律の演奏家にとっては「それしか」出来ません。
旋律の「音程」
かつて、幻の(来日後は幻で無くなりましたが)名指揮者セルジュ・チェルビダッケ氏が言った名言に「最初の音を聴いた時に、最後の音がわかった。」というのが在ります。
すなわち、最初の音が出た瞬間に、もう最後の音は決まってしまうのです。
楽譜はその関係を正確に記した音楽の設計図ですから、最初の一点から測って行けば、自ずと最後の地点にたどり着くという意味と、その中にある意味を知れば、当然として最初から最後までの音が判っており、その様に全体の音が配置されなくては成らない、との意味です。
彼の主張した、「音楽現象学」の真髄でしょう。
我々が話をする時の様に、ただ何となく言葉を重ねて行くのは、決して芸術的な話とは言わないのと同じで、しっかりとした主張をする時は、構成を考え言葉を選び訴えるのですが、そこまではこの様な文章を書く事と同じです。
しかし、講演などで話をする時にはこれだけでは聴衆に感銘は与えられません。
聴衆の関心を引く為にも、主張がより強く印象に残る為にも、ストレートな表現ばかりで無く、時には刺激的な展開も考えて、それを演じる事で講演するのです。
音楽では、その台本が「楽譜」です。その中の最も直接的な指示でもあり、表現その物が書かれているのが旋律でしょう。それで、チェルビダッケの言う言葉通り、予定した筋道をたどり、結論に達する様にしなければなら無いのです。
「少しぐらいの脱線」があっても最後にたどり着けば良いのだと、思うわけですが、音楽では話の様には自由な展開は出来ません。
「少しぐらいの脱線」のつもりが、全く本題を打ち消してしまう可能性だって十分に考えられます。
もちろんそうなっても、聴いている人達の中に「これは本題を逸脱している。」と判ってしまう人は少ないでしょう。ただ何となく「下手だ」とか「つまらない」、場合によっては本来無い興奮をさせられ「感動した」と、勘違いでその演奏を「新しい解釈」と思い込んでしまう場合も少なくないのです。
少し前置きが長くなりました。
旋律の「音程」は、ハーモニーの「音程」と違うのでしょうか?
基本的には変わりません。「ド、ミ、ソ」の旋律も、一度に鳴るハーモニーの「ドミソ」も同じ音程と思って構いません。
この時の良い「音程」は、「純正律」の「ドミソ」が正解です。Sound 2.正 Sound 3.誤
「ソ、シ、レ」も「純正律」の「ソシレ」と同じですが、少し気を付けなければ成らないのは、この「ソ」を主音にした「純正律」ではだめです。そうすればこのハーモニーは大変に整って美しく響き、属調(元の調の完全5度上の調)に転調した事に成ってしまいます。「ファ、ラ、ド、」も同じです。
ではすべての音階の音は、「純正律」の音程で良いじゃないか。と結論付けてしまうでしょう。
確かにこの様に、その調のトニカ(主和音)を始め主要な三和音は「純正律」の音程である事は大切です。しかしそれはこの様な分散和音で進んでいる旋律の時、です。
すなわち旋律は、いつもハーモニーする音だけでは出来ていない事を、もう一度確認して頂きたいのです。ほとんどが1つおきに「ハーモニーの音」と「ハーモニーしない音」が現われてくるのです。
例えば、「ド、レ、ミ」は「ド」と「ミ」はハーモニーの「和声音」ですが、「レ」は経過音というハーモニーしない「非和声音」です。これを「純正律」の「レ」にすると何とも「間の抜けた」低い音に感じます。むしろ「平均律」か、もう少し高い「レ」の方がスムーズな旋律になります。
他のパートに「ドミソ」のハーモニーが有ればなおさらです。
ここで「非和声音」の復習をしましょう。「音楽のマニュアル」でも説明していますが、ここでも簡単に説明をしますと、ハーモニーの中にそれを「じぁま」をする、ハーモニーを「歪ます」働きをするような音の事です。種類は5種類だけです。(譜例3、)
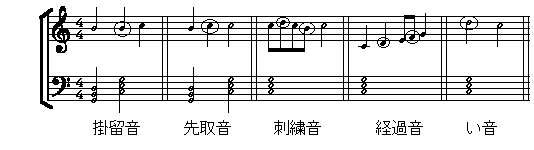
譜例3、非和声音
これらの「非和声音」が有って、旋律が滑らかに「意味有る」音の動きに聞こえるのです。
これらがすべて整ったハーモニー「してしまう」音なら、この「非和声音」は存在しなく成ってしまいます。
これも、「純正律」が「平均律」に主役を譲ってしまっている理由でしょう。
少し込み入った問題を提起します。「ソ、シ、ド」の旋律はどの様になるでしょう? もちろんこの「シ」が問題です。
「非和声音」譜例3、の中の掛留音のような旋律で、最初が「ソ」とすれば、明らかにこの「シ」は「非和声音」の「い音」にあたりますので、かなり高くして「導音」の性格を強く出した方が良いでしょう。
しかし、この「シ」がもう1拍早く動けば「ソシレ」の第3音の「し」ですので、「純正律」の「シ」が良いという事に成ります。でもここが問題なのです。
この「ソ、シ、ド」の旋律は、ハーモニー分析する前に、この旋律の意味を考えておかなくてはなりません。
前後の問題は有るので、この旋律の時は絶対にこうだと言う事では有りません。その場で考える必要があります。
今はこれだけの旋律として考えます。
この旋律にどのようなリズムを当てはめても同じで、明らかに「ド」へ向かった旋律、「ド」を言いたいが為の「ソ、シ」です。
それならばその「意思」をよりハッキリするには、「ド」に近い「シ」の方が良い訳です。
すなわちこの「シ」の音は、その他に音がありそれが、「ソシレ」のハーモニーを作っていたとしても、そのハーモニーの中の「シ」ではなく、「非和声音」としての「シ」である方がこの旋律の「意思」を伝えられるという事です。
難しそうな複雑な説明でしたが、実際に歌ってみて下さい。まずほとんどの人はその様に歌います。
これが「普通の感覚」なのです。
そうであるはずなのに、いざ演奏の時にはハーモニーに捕われ過ぎて、「普通でない音程」で演奏してしまうことが多いのです。
実証実験
少し話題からはずれますが、中高の学生相手に合奏指導する時、全員に目をつぶらせて演奏させると、素晴らしくアンサンブルが良くなります。
それは、自分たちで聴き合わせながら演奏する事で、一人だけ取り残されたくないので、一生懸命他の人達の中へ入って行こうとするからです。
その合い方は、ビックリするほどですが、しばらくそれに慣れてくると、今度は音程がそれこそビックリするほどピッタリと合ってきます。
しかしもっと続けるとだんだん飽きてきてしまいます。
この様子は、今説明している正しい音程を上手く説明した例になります。
まずは、音程に関心は少ないし、全員が一致して認識できる「基準音」が無いので、音程は全くバラバラですが、テンポのずれはすぐに判ります。
何とかして大体合って来ると、合った時の音が、「基準音」に成ります。すると次の音が決まって全員が同じ音を出そうとします。
それも最初は、基準音がなかなか同じに成らない間はまだそろいませんが、何か1つの旋律が終れば、そこで基準がはっきりします。そこでみんなの意思が1つの「基準音」に集約されるわけです。
後は技量次第で、しばらく思考錯誤の後、かなりピッタリ合って「しまいます」。
問題はその後です。
皆は、一生懸命合わせようとします。しばらくすれば、合います。その後も大体合ってきます。
すると、今度は「飽きて」しまうのです。これが人間の本質でしょう。
音楽では、「合わせる」事が一大目標です。音程もリズムもテンポも、小さい時からそればかり注意されて来た様に思います。それがいざ合ってしまうと、「面白くない」のです。でも「合っている」事は、絶対なのです。
それは崩せないのです。「意図が無ければ」です。 この「意図」が、先ほどの「普通の感覚」の「シ」の「音程」です。
世の中と同じで、まわりと「同じ様にする」事は「違う事をする」より易しいのです。
「違う事をする」には「意思」がいるのです。「違う事をする」事で、意見を言う事が出来、存在価値が生まれるのです。
もちろん、知らず内に「違う事をする」場合はありますが、それは多くの場合埋没します。埋没しなければそれは粗野でやかましい演奏でしかないのです。
それを「意図」と勘違いすると、聴衆もその「力」に興奮し、「感動した」と勘違いしている事も少なくありません。
先ほど「いざ演奏の時にはハーモニーなどに捕われ過ぎて、「普通でない音程」で演奏してしまうことが多い」と述べました。この場合でも確かに「意図」が有ります。「ハーモニーしなければ」との「意図」です。
それなりに主張があるでしょう。ですからこの様な演奏には「真摯」な印象を受ける場合もあります。あるいは、良い意味で「宗教的敬虔さ」に思える場合も無くは有りません。しかしそれを「強要」されるような印象も併せて持つ事を、理解しておくべきでしょう。
音楽の他でもその様な事はあるでしょう。注意深く聴き取らなくてはいけません。
それだけ「違う事をする」と「意思」が現われるのです。
「何もしない」は「何もしてはいけない」に思えるのです。「何もしない」表現は、「普通の感覚」でなければ成らないのです。
ではこれらを踏まえた上で、意図有る「音程」は何処をどの様にすれば良いのでしょうか。
何処にあるか
もちろん楽譜上から、その部分を探す事から始めます。
最も簡単な見つけ方は、何となく「普通の感覚」で音符を演奏していくと、「間違えそうになったり」、「やりにくかったり」、「響かなかったり」、した所がそうです。
ようするに「普通」で無いからこの様に成るのです。ただし、ある程度の技量が必要です。ある程度とは、各調の音階、各分散和音がスムーズに出来ることです。ここで詰まっては、「普通に感覚」が詰まっている事になります。
それは聴衆にとっては「特別な感覚」に成ってしまうのです。
ですからどうしても「スケール」と「アルペッジオ」の練習は、絶対に身に付けなければなりません。運動の「柔軟体操」です。音が自由になる準備運動です。
「スケール」も「アルペッジオ」の練習は、すべてで無くても構わないと思います。
全調は必要ですがスケールは「ドレミファソ」「ラシドレミ」アルペッジオは、「ドミソ」「ラドミ」だけで十分でしょう。
ようするに、最も基本的な音の動きだという事です。「ドレミファソ」と「ソラシドレ」は同じ、「ドミソ」と「ソシレ」も同じです。
なぜかはそれぞれの「音程」の並びが同じだからです。その代わり全調必要です。
これを怠ると、「普通の感覚」が崩れます。
この感覚を基に探せば意図有る「音程」は見つかります。
音の跳躍した所は要注意でしょう。和音の転回した時も含めてです。やはりそこには「普通の感覚」では無いエネルギーが必要です。それはなぜか? 「意図」が有るからです。
ただしあまり隣り合った音ばかりで見ていると危険です。「木を見て森を見ず」の可能性は有ります。せめて2~3拍間か2~5個程度の音符で見れば十分に思います。
もっと大きなフレーズで見ないといけない場合もありますが、それは次の段階の問題として、自然に見えて来る様に成ると思います。
如何にすれば
見つかった場所の「間違えそうになったり」、「やりにくかったり」、「響かなかったり」、した音への「音程」はもちろんですが、その「音程」だけで無くその音と、その音の行き着くべき音(解決する音)との関係も見るべきでしょう。
本来行き着きたい音を強調する目的がこの「意思」には有るのですから、ただ「普通の感覚」で無ければ良い訳ではないのです。行き着く音は全体からすれば、「普通の感覚」である事は多いです。ですから強調したかったのですから。
そこヘ行くには、行き易い「音程」が「いる」と言う事です。ハーモニーし易い音ではありません。反対にストレスが掛かる「音程」です。「ストレスが強ければ強い程」、行き着き感(解決感)は強いはずです。
弓は強く引けば強いほど、矢は遠くへ飛ぶでしょう。しかし限界を超えると「折れ」てしまって元も子もなくなります。それも音楽は同じです。余り調子に乗って強すぎると、聴衆は違う物を思ったり、耳をふさいでしまいます。程ほどに。
大概は、その目的音に近い「音程」が上手く行く場合が多いです。
音楽は、隣り合った音がストレスを持つ事は、「非和声音の経過音や刺繍音」でお解りと思います。
「普通の感覚」は、完全1、8、5、4度、長短3、6度の「音程」順でしょう。幹音(臨時記号の付かない音階の音)間では増4度が最もストレスを持つでしょう。例えば「ファ/シ」です。
この音程の興味深い例があります。
「マリア」の例
バーンスタインのミュージカル「ウエストサイドストーリー」の、最も印象的なモチーフ、トニーの歌う「マリア」です。
「ファ、シ、ド」です。この「ファ、シ」が増4度音程です。これは、「ド、ファ#、ソ」とも、短調で「レ、ソ#、ラ」(この様に使われる所もあります)「ラ、レ#、ミ」とも読めます。
今短調でも長調の意味合いと同じ(サブドミナント→トニカ)ですので、長調での2つの音の取り方の違いを考えます。
サブドミナントからトニカに行くのは、ハーモニーでは「アーメン終止」と呼ばれ、キリスト教の「アーメン」を唱える音程に使われます。(譜例4、)旋律では「ファ/ド」です。
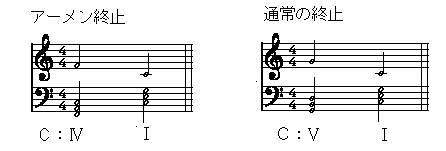
譜例4
「シ」は「ドミソ」にも「ファラド」にもありませんから、「非和声音」である事はまず間違うことはないでしょう。無理に「シレファ」のハーモニー(vii。)にすれば、出来なくは無いでしょう。
この「無理に」をしようとする事があるのです。意外に多い事です。
先ほどの注意で、前から順にしか考えない時には、特にハーモニーで理解しようとすれば、これは良く起こる事です。
この増4度は音を出し難いのです。歌は特に歌い難い音程の代表です。
それでも何とかと考えると、この様な「無理に」ハーモニーを設定しなければなら無くなります。
とりあえずこの音程は(音楽学校では習うので)「歌え」ました。しかしまたその「シ」から「ド」へはかなり難しい事に成ります。その様にして歌えても、これは良く知っている何とも「切ない」旋律とはなりません。ここだけ取り出して聴けば、「下手な歌」に聞えます。
また、この「ファ/ド」の音程を「ド/ソ」と取ってしまう事が有ります。
この場合には、調性感の問題が絡んできます。
特に日本人の持っているイントネーション感で、歌い出しの所だから、「ド」からと思ってしまうとこれは、「ド、ファ#、ソ」と取ってしまうでしょう。
この「ファ#」はかなり「ド」との関係の遠い「音程」関係にあります。そこで同じ様に「ファ#ラド」のハーモニーを設定しようとするのですが、やはり無理があるので上手く行かない事に成ります。Sound
2
そこで頼りにするのが「平均律」と言う事に成ってしまいます。
やって見てすぐに判ります。思ったような旋律感にはならないのです。Sound 3
この様な試行錯誤が続くのです。聴いていれば(頭の中では)何とも無いのですが。
解決方法は、「ド」を歌うつもりで「ファ→ド」その、「ド」を歌う時に少しそこに上がりきれなかったような「シ」を出せば出来ます。Sound 4
この試行錯誤を実際に聞く事が出来ます。ホセ・カレラスの・レコーディング中の音源がありますし、サウンドトラックでの他の人の歌も聞き比べられます。大変に興味深いです。
この様な試行錯誤の結果や、間違って歌ってしまった例を聞く事が出来ます。
作るほうも聴くほうも何でもない「普通の感覚」が、演奏ではいかに難しく成ってしまうかをお判り下さい。判ってしまえばそんなに難しくは無いのですが。
ようするに解決するには、楽譜をしっかりと研究する事しかないようです。
では、最後の注意点の「音色」に進みます。 これも前の章で同じ問題を取り上げましたが、さらに注意するべき事を述べます。
この章を終りにしたのは、意味のある事です。それは、「音色」は今までのすべての問題を含んでいると理解して頂きたいのです。
前章の2.音の表情 の A、発音 B,イントネーション C、音色 と、この章の ①テンポ ②リズム ③音程は、全てこの④音色 に集約出来るのです。
音色は、かつて物理的には倍音の質と量で決まると言われ、その後はその音の立ちあがりこそ決定付けると心理学で言われ、打楽器やピアノでは音の切れで決まると言われてきました。
その真偽の議論はその道の専門家に譲るとして、演奏家が考えなければなら無い事、全てのテクニックを駆使してしなければ成らない事は、音の表現です。
すなわち、「音色」が全てといっても言い過ぎとは思いません。別の言い方をしますと、「音色」をどの様に決定するかを考えれば、全てを考えなければ決められないのです。
一般には、「重い音」「柔らかな音」「大きい音」等などと音色を決めるのですが、それはあまりに大雑把な事です。むしろその様な事を考える様では、良い演奏とは程遠い感覚です。どの様に重いのか?どの様に柔らかいのか?どれだけ大きいのか?それが表現なのであって、極限の演奏を期待する訳ではないのです。
もしそうであるなら、楽器を変えたり他の方法を作曲家は考える事でしょう。彼は貴方のその楽器や声での表現する事を望んだのです。
「音色」と言うよりも「ニュアンス」のほうが合っているかもしれませんが、それでは表現の幅が狭く成っているように思えます。
落語家がどんな人物でも一人で演じる様に、我々演奏家もどの様な「人物」「事象」「物」「風景」でも音で演じなければならないのです。
それは「ピッチ」「長さ」「ダイナミック」「リズム」等楽譜に書かれている事だけでは表現は出来ないのです。そこから内容を読み取って理解した上で、最もふさわしい「音色」を「作り出す」のです。
「これこそ、我々演奏家に与えられた、「創造的」アクションなのです。」
我々演奏家は良い音を出す為に日夜努力しています。その「良い音」を一度良く考えて見る事が必要でしょう。
もちろん声やそれぞれの楽器として発声や奏法を整えて、コントールの効いた声や音を出す事の為の練習はもちろんですが、さらに一歩進めて、どのような「良い音」を造れば良いかを考えてみたく思います。
「良い音」は「良い響き」と置き換える方が音楽の上では良いかもしれません。すなわち「良い音は」「良い響き」があって成るものですから、我々音楽家は「良い響き」を求める努力をしなければならないのです。
一言で良い響きと言っても、この様なものだと説明できるような物ではありません。しかし、一度聴けばこれが良い響きだとほとんどの人が判るものです。
もちろんまだ音楽の追求が不充分な演奏家はまだ判らないかもしれませんが、それは、そのような「良い響き」にめぐり合った事が無いからかもしれません。
残念ながら、これは体験した方にしか解らない事なのですが、本当に良い響きは大袈裟ではなく「至福の時」を与えてくれます。それこそ言葉では言い尽くせない「良い音」です。
それは、自分で再現できるかどうかを、考えることすら無いかもしれません。それこそ「才能有る」人にだけ出来る「特別な物」と思っているからでしょう。
そのような神様の領域に至る論議など、もっての他と思われるかもしれませんが、敢えて少し立ち入りたいと思います。
「良い響き」の体験は中々出来るものではありませんし、たとえそれが録音されてもその経験された物と同じものと思えない事が多々あります。多分に心理的な影響も大きいのだと思いますが、その点に今は触れないでおきましょう。純粋に音として考えて見たいと思います。
録音された「良い響き」が在れば良いのですが、中々そのような音源はありません。私の所有しているCDの中で最もこれに近い物で分析をして見ました。
これは、かなり古い演奏ですが、
Metamorphosen, Studie fur 23 solostreicher Cond. Clemns Krauss(31thMarch 1893 - 16th May 1954) Orch. Bamberger Symphoiker 1953 /amadeo423 416-2 /No.0060
というCDに録音されている音源をもとに検証しました。詳しくは「名演奏のマニュアル(未完、1部公開)」に検証結果を載せます。この演奏は、筆者の所有する音源の中で、何度聴いても「良い響きだ」と感動をさせてくれる数少ない一つの物です。
それぞれ皆様も、この音にも勝る物と思われるものをお持ちかもしれません。また、この程度の物ではない、本当はもっと良い響きだと言われると思います。ただ今客観的に手に入る(今は中々難しいですが)物は、筆者の手元にはこれしかないのです。
この様に録音として残る事は稀です。筆者も自身のCDの録音で、その時はとても「良い響き」がしたことがありましたが、それはCDには記録されていません。残念です。
その音は「心に染み入る」「胸の透くような」等の言葉で表現が出来ると思います。このような言葉による印象で実際の音を説明するのはかなり無理があります。そこでこのCDの音で解析を試みたわけです。
声紋分析でこの音を見ますと、倍音の縞がくっきりと規則正しく並んでいます。(「名演奏のマニュアル」の検証結果参照)
他の音の場合も倍音がたくさんあるのですが、この音の様にハッキリとした縞模様が現われることは稀です。
これは、低次の倍音が周期的に重なっている事を示しています。
倍音は整数倍の振動数の音ですが、1、2、4、8、16、32、64、の倍音は全て同じ音名の音です、3、6、9、18、36、72、も同じ音名の音です。5、10、20、40、80、も同じです。7、14、28、56、102、も同じ。と、だんだんと少なく成って行くのはお判りと思います。
すなわち基音になっている音名の音、その完全5度上の音名の音はドンドン沢山鳴りますが、それ以上は極端に少なく成って行きます。音楽で言えば、主音と属音は、多くの倍音を持っていますが、その他の音はあまり多くは無いと言う事です。
この主音と属音の音程は、完全5度です。この関係は長調でも短調でもあるいは色々な旋法と言われる音律でも必ず出てきますし、重要な音としてあります。それはそのはずで、物理的に大変に整った音の関係にあるからです。
これらが多いほど安定した整った音(響き)がしていると言えます。もちろんこの音だけで無く5倍音も主音と長3度の関係にあります。すなわち長3和音(ドミソ)はこの様な音から出来ていると言うことです。整った響きのはずです。
完全5度の音が重なるとあまりの関係の強さに、むしろ特別な束縛感を感じてしまう事あります。そこで和声学や対位法でも「並行5度」は避ける様に言われます。しかし響きとして見るには、この完全5度の関係が完全に出来ている事がよい響きの第1です。
音響学の世界では、「平均律」の「狂い」くらいはわずかで問題は無いと言われますが、その違いに気が付かない様では「良い響き」は得られません。
その中に他の低次の倍音が混ざれば、この様な澄んだ響きを作る事が出来るのです。
別の言い方をすれば、この様な完全5度の関係や低次の倍音の関係が狂えば、響きが濁ってしまい、物理的により高い倍音が出難くなり、変わりに他の音名の音が混ざってしまう事に成ります。それが「良い響き」が作れない原因です。
この様な「心に染み入る」「胸の透くような」響きは、本当に心地よい感動があります。
これは体験しなければ理解は出来ないと思うのですが、一度出会うともう音楽の魅力にはまってしまいます。それほどに強烈な体験です。
音楽家にとってこれは究極の目標であるのですが、それこそ狙いはするのですが、偶然と言っても良い確率です。しかしそう言ってしまっては私のこのような「演奏マニュアル」を書いている意味が無く成ってしまうので、せめてそのような偶然が起こる確率を高める為の努力を考えます。
それには、今まで音の説明を延々として来ましたが、ヒツコク申し上げている「動き」「変化」が大切です。
ある音が、最終目標の音に向かって進む「動き」が表現されて、その最終目標にたどり着いた時、この様な「良い響き」がします。
最初から最後まで全ての音が「良い響き」でありたい訳ですが、それはベーシックな音の問題です。
もちろん、全ての音ができる限り「良い響き」を持つようにするには、日夜努力をして、せめて自分が納得する様に「磨く」事です。
自分が納得してしまえばそれで終りますが、実際は飽くなき欲求です。もし納得してしまえば、そこでその人の魅力は無くなってしまうでしょう。
演奏中でも同じです。「次はもっと良い音を、」と、思いながら演奏しています。
その「次」は、すぐ後ではないのです。「次の目指すべき音」なのです。その様に繰り返し、最後の音へ向かう事が「良い響き」の追求です。
その関係は「フラクタル状態」であるのですが、言葉を変えれば「入れ籠状態」、つまり箱の中に箱が、またその中に箱と続いている状態です。
この様に繰り返せば、最後に最も素晴らしい「良い響き」がするはずです。もちろんこの最後とは、クライマックスである場合が多いのは言うまでもありません。後はその余韻を楽しむ様に作られる事もあるでしょう。
この様な「紆余曲折」を通って行き着く事を、「ドラマがある」と言うわけです。
「ハラハラドキドキ」しながら最後に「どんでん返し」があるドラマが、最後に素晴らしい感動へと繋がっていくのは、小説や映画だけではありません、この音楽も同じです。
しかしその「紆余曲折」の過程で、「良い響き」が無ければ、またその向こうに「良い響き」を期待できず、ゆえにこのドラマそのものが魅力無いものに成ってしまうでしょう。
細部も「良い響き」、それが積み重なってより良い響きへと「発展」しなければ成りません。その変化が、音楽の持つ「意味」であり、その細部の「音」や「旋律」の関係が「論理性」なのです。
その様に音楽に「意味」や「論理性」を持たせるには、「響き」の主張が必要です。ただ単に「美しい音」だけではそれに「主張」はほとんどありません。
全員が「純正律」の音程で、バランスを整え一糸乱れず演奏をするのは、大変に「ストイック」(禁欲的)な「主張」となるでしょう。もちろんそれを作品が求めているならもちろん正解でしょう。
それでもほとんどの音楽は、対比的な物語があり、それをさらに転換する事で対比的な主張をする場合が普通です。
そこで知っていて頂きたい事は、「音楽は、悪を表現できない」 事です。
「悪い事」「汚い事」「嫌な事」等は、表現出来ません。
そう意味では、「美学」とは音楽の為にある言葉かも知れません。疑問に思われると思いますが、少し考えてもらえれば「これらの表現は出来ない」事に気付かれると思います。
「では」です。全て肯定的に捉えて、表現して行くしかないのです。
後に詳細に解釈をする「エグモント」の中でも、エグモント伯を死に追いやった新総督アルバレスは、戯曲の中では、大変に「冷酷」な人物ですが、「冷酷さ」は断固とした意思の強さ毅然たる態度が強過ぎるほどに有って、やっと表現出来るのです。
モーツアルトも「魔笛」に在って悪の代表「夜の女王」を、ヒステリックな表現として、とんでもなく高い音(6F)を出させ、コロラトゥーラの技巧的スリリングな音楽でしか表せませんでした。
ワーグナーに至っては、背徳的な題材を甘美に表現し、最後に救済の音楽で締めくくる構成がほとんどですが、その背徳的な題材の甘美な事は、「ただ素晴らしい」と言えるでしょうし、その内容を知らずにいれば、その部分をまるでタンホイザーの様に「ヴィーナスの愛欲に捕われる」ように成ってしまいかねません。
R.シュトラウスの「サロメ」「7つのベールの踊り」を、中高生の女の子が喜んで演奏するのは、心情的には解らなくは有りませんが、目的を考えれば「?」です。オルフの「カルミナブラーナ」の「性開放の歌」を青少年が演奏し、学校関係者やPTAが拍手喝さいするのを見たら、オルフは驚くでしょう。
確かに刺激的で美しい音楽です。しかしその後に来る「救済」や「改心」の為の対比的表現である事を忘れては、その美しさの意味が違ってきます。大変に注意しておかなくては成らない事です。
ただ最終的な結論が、「救済」や「改心」であってもそれが何時も「ストイック」な表現である訳ではありません。
むしろそのような表現も、その後にある「開放」が目的のはずで、「宗教的」「道徳的」内容であっても、それはあまりに短絡的に「言葉」で考えた表現(意味づけ)でしょう。
「宗教的」「道徳的」な「救済」や「改心」の表現も、「至福」の「良い響き」に昇華して行くように考えて欲しく思います。
以上の演奏上の注意点を理解の上、次の「5.演奏の解釈」に進んで下さい。
← <3.奏法の知識> へ戻る
⇒ <5.音楽の解釈> へ
「演奏のマニュアル」のプリントアウトは、御希望者が多ければ考え様と思います。
B5(またはA4)で95ページほどに成りそうです。
もし御要望があれば御知らせ下さい。検討いたします。