|
|
「演奏のマニュアル」
演奏法
<3. 奏法の知識>
「はじめに」の所にも書いていますが、この「演奏のマニュアル」では、それぞれの楽器の奏法や声楽での発声法についてを論じる物ではありません。
と言いながらもそれらの知識と全く離れては説明不可能な事も有りますので、それぞれの専門的知識が有る事が前提になってきます。
誰でもが全ての分野の奏法を知っておければ良いのですが、まさかその様な事は不可能でしょう。
たまにあらゆる楽器を扱えるという方に会いますが、ただ鳴らせる程度の場合が多く、むしろたった一つでも専門的な知識を有する方の方が今からの説明は理解し易いでしょう。
1つは必ず専門の演奏法を習う事をお勧めします。
すなわち、その専門知識により他の色々な問題点の理解への入り口になるからです。確かにほとんど先生に付かずに、独学で立派な演奏をされる方もいますが、その人は良いのですが、その人に習う生徒や他の演奏家とのコミュニケーションにおいて、視点や言葉だけで無くアカデミックなアプローチが出来なく成ってしまうかもしれません。ぜひとも1つは習って下さい。
ただ、これだけは少しは知っていてもらいたい発声法や各楽器の奏法が、いくつかあります。
1.発声法:
もちろん声楽のレッスンで習うのですが、声は誰でも普段使っているので声の出し方はみんな専門家です。しかしただ普段の声の出し方ではなく、やはり「良い声」の出す発声法の知識は少しは知っておいて下さい。少なからず役に立ちます。
2.ボーイング:
弦楽器の奏法で弓の使い方の事ですが、実際にできるに越した事は有りませんが、せめてその考え方は知っておきましょう。モーツアルトもベートーベンもその方法には精通していました。他にも多くの作曲家達も弦楽器の専門家がたくさんいます。
特にスラーの記述は1800年代中頃までは、通常の我々の「滑らか」にする使い方で無く、単にボーイングの指示です。
3.ピアノ奏法:
作曲家達は、ほとんどピアノを使って作曲をしています。特にピアノの得意な作曲家達は、そのフィンガリングにまかせたパッセージを好んで書く傾向が有ります。
それだけでなく、やはり今の演奏家達も音楽大学入学の為に少しは習ったことでしょうし、ピアノを伴奏してもらう事は頻繁にあるのですから、全く触った事も無いのでは理解は難しいでしょう。少しは弾こうとして下さい。
やはりピアノは楽器の中心です。その音は演奏の基本とも考えられます。
4.作曲法:
「エイや!」と、思いつくままに作曲をしている等とは、まさか思っていないと思いますが、作曲家はコンポーザーという様に音楽を構築して行く仕事をする人です。
それであればその方法論の典型を知ることは必要でしょう。むしろ和声学は簡単ないくつかの名称程度で良いですが、対位法、ソナタ形式、ヴァリエーションの方法などは知っておきたいものです。
等です。 必要に応じて少しは解説を加えたいと思いますが、一応簡単な音楽事典にのっている程度の知識はあるものとして話を進めます。
良く言われる演奏技術の当面の目標は、「話す様に(歌う様に)演奏できる事」です。すなわち声が目標だと言いたいのです。
では声楽家達は何の為に学ばなければ成らないのでしょうか?
もちろんより良い声を得る為は理解できるでしょうが、それだけではありません。
その良い声では、思い通りにコントロールが中々できないのです。
普段使っている声でも一定の音程を維持しながらとか、指定通りのリズムとかになると練習が必要でしょう。でも普段の声だとそれなりに自分でトレーニングができるかもしれません。しかし、良い声でそれを行うのには、体全体の使い方を知ることが必要です。
その為には、音楽以外に身体の構造や機能も知りたい所です。体が楽器なのですから。
弦楽器は見た目にも、人間の体を模倣しているのは一目でしょう。ピアノも見方によっては、少し肥満体ではあるけれども人型のようですね。
では管楽器は?
楽器だけを見れば確かに人の体の様ではありませんが、ではどこにそれがあるのでしょう?
答えは、自分自身の体です。実は声楽と同様に、体自体が弦楽器の胴の役割をしています。といいますより声帯の代わりが管楽器そのものなのです。やはり人の体の構造には無関心ではいられないですね。
ではそれを使ってどの様に音楽をするのでしょうか? 考えて見て下さい。
音を出し、一定の高さで、一定の長さで、自由に音色やダイナミックをコントロールして、作曲家の意図した音楽を再現する訳です。
そこで、それぞれの音の表情「発音」「イントネーション」「音程」「ダイナミック」「音色」を考える為に、知識を得る必要が出てきます。
その後やっと、<演奏上の注意>をふまえて、<音楽の解釈>の段階へ至れます。
どの様に音を出すのか? それはその時々によって違ってくるでしょう。ですから知識が必要です。
何の知識でしょうか?
我々にとって日常体験している音は、どの様な音かです。
それは当然知っているでしょう。しかしそれを出すことは大変に難しい事です。それができる為には、まずはそれを良く知ることから始めなければならないでしょう。
今、鉛筆を床に落としたとしましょう。床は絨毯のような柔らかい所では音はしないでしょうから、ある程度固い床です。
「チリリリン~」 変な擬音語で恐縮ですが、大概こんな所でしょうか。
鉛筆全体が上手く落ちれば少し音程が高くなりますが、それは稀ですので意外に高い音で、それが何度か繰り返されますね。
やって見ないで想像だけだと、「コロコロ」でしょうか。全く現実とは違いますね。
さて音楽をしようとする我々にはこの程度ではまだ足りません。
「どの様に音が出始めているのでしょう?」(A、発音)
「どの様に伸びているでしょう?」(B、イントネーション)
「どの様に終っているのでしょう?」(C、フレーズ)
「どの様な音色でしょう?」(D、音色)
これらが解かって始めて再現できるのです。
*実際に鉛筆を落とした音。Sound 1(クリックすると音がでます)
波形スペクトル(図、2)

図、2
音楽においての音の出始めは、「発音」と言う言葉が適当でしょう。
もちろん言葉の「発音」から来ていますが、ピアノや打楽器でもその音の立ち上がりの事を言います。もちろん管楽器でも言います。
先ほどの鉛筆を落とした音の発音は、波形スペクトルからも解かるように、はっきりと立ちあがっています。
良く考えて見ますと、実はこの様にハッキリとした立ちあがりの発音以外の方が少ないのです。
あえて探すとするならば、風の音、サイレン(自然の音ではありませんが)、他に何かあるでしょうか。あまりたくさん思いつきませんが、自然の音ではない音のサイレン、お化け(実際には音も姿もありませんが)の登場でしょうか。
ようするに「非日常」の音としての役割に成っている場合です。
結論を言えば、基本的には「ハッキリ」とした「発音」がほとんどであり、特別の表情として「あいまい」な「発音」立ちあがりが有ると言う事です。
我々は、音楽であろうとも日常に聞かれる音を基準にその表情を判断しているのには、間違いありません。
と言う事は、音楽の「発音」において、「あいまい」な「発音」は、特別な表現を除いて基本的にはしてはいけないのです。
どんなに「優しく」「柔らかく」「静か」であっても、「ハッキリ」と優しく、柔らかく、静かに「発音」しなくてはいけません。
もちろんピアノ弦楽器打楽器などは、それしか「発音」できないはずですが、管楽器や声楽(もちろん上手な人ではない)では意外に適当にされています。
管楽器のテクニックとしては「タンギング」です。ですから、教則本の1番最初に 「"Tu" と音を出しましょう」と、始まっているはずです。
こんな所をいいかげんに済ました人は、多いのではないでしょうか。
声楽家の中には、考えもしなかった方も多いでしょう。わざわざ考えなくても、出来てしまう場合が多いのは確かです。でももう一度しっかりと認識して下さい。
上手な名歌手達は、ずいぶん気をつけて「発音」を考えています。
弦楽器奏者も、上手い人達は、必ず弓を弦の上においてから引き始めます。
ピアニストも鍵盤に指をほとんど付けてから弾きます、決して叩きつけません。
打楽器奏者も、上からマレットを叩きつけるので無く素早く跳ね返らせる所に集中しています。
もちろん管楽器奏者は、必ずタンギングをしています。
これらのテクニックの実現ために絶対的に必要な事は、実際の「発音」の前に "ため" とも言える「準備」がいります。
これを音楽では、「アイン・ザッツ」(Ein Satz)と言ったドイツ語の用語を使います。
これは音を出す為にだけではなく、複数の人達と合わせる為のアンサンブルのテクニックとしても重要です。
言葉の発音で理解するならば、子音を発音する直前には少しでもこの "ため" を必ず自然にやっているはずです。すなわち子音を持たない母音だけの発音はし難く、不明瞭に成る危険性が有るのです。ですから合唱など歌の指導では「h」を付ける様に指導する事が多いのです。
もちろん名歌手達はそんな事をしなくてもちゃんと発音できるテクニックを持っています。
子音にも色々な種類が有るように、破裂音から優しくキスする様なタッチまで無限に在ります。
そして、次にこのように「発音して」出した音を、どのように伸ばすかを考えます。
「どの様に伸びているでしょう?」の答えにこのイントネーションの言葉はふさわしくないとお考えになるかもしれません。
今まで筆者の各マニュアルでも述べておりますが、この用語は、西欧では「音程」「リズム」「音色」まで音楽のすべてを含んで使われると言って来ました。その通りです。
このような疑問を持たれた方はきっと、音を一つの音符に置き換えたのだと思います。
発音と同様に、一つだけ機械的に伸びる音は自然には有りません。スピーカーのハウリング音の様な、自然には無い音でしょう。
いったん出た音は、鉛筆の音の場合はきわめて早いですが、徐々に減衰するのが普通で、自然界ではこれがほとんどです。反対に増幅する物もありますがその後はまた減衰していきます。例えば「波の音」の様に。
音は、必ず変化する物と考えたいです。
旋律も本来は、1つの音がだんだんと音程が変化するのをいくつかの音符にしたに過ぎません。そこに何らかの気持ちを付け加えるために音量や音色の変化を加えて表現するのです。
すなわち「音の伸び方」は、音程、音量、音色など、音楽の大切な要素イントネーションをほとんど含みます。
打楽器やピアノ奏者は、奏法は打鍵の一瞬に集約しますので、前項の「発音」がすべてと考えるでしょう。
確かにそうですが、その一瞬は何のためか考えてください。
その後のこのイントネーションの為でしょう。
この部分こそが、音楽の音の表現における「最重要部分」です。
それぞれの要素は後の項目でも問題になってきますが、ここでは、ぜひ知っておいてほしい知識について述べていきましょう。
音程は、大変に複雑な難しい問題を含んでいます。弦楽器 管楽器 声楽の方々は、一度とならず苦労をされているのでよく分かると思いますが、ピアノや打楽器などの方々は調律の為としてしまうので、問題を起こしている場合が少なくありません。
大きな原因になっているのが、「平均律」です。
その対極にあるのが「純正律」ですが、それらの詳しい説明は私の「音楽のマニュアル第2部」などをご覧ください。
簡単にいえば、自然界の物理法則に従った整った音の組み合わせを「純正律」、1オクターブ(倍の振動数の間)を均等に12等分したのが「平均律」です。
結論から言えば、大変に複雑で難しいこの問題を一気に解決をつけようとしたのが「平均律」であり、大変に優れた物であります。したがってピアノなど「平均律」で調律されている楽器がほとんどですし、その音律で演奏する事は、「おおよそ」には問題ありません。
しかしその「おおよそ」であるという前提条件を知っておく必要があります。
「平均律」が発明された状況としては当然アコースティックな音環境であり、大変に残響や反響の多い教会などであった事です。
このような環境では音がお互いに干渉を繰り返すことによって、互いに影響を与えて音は純正(律)に響くように変化していきます。
ピアノもそのような音の干渉機能を楽器の中に持っています。だから大きなコンサートグランドピアノが良い音がするのです。
打楽器であっても胴や共鳴管、演奏している空間自体がそのように機能します。その意味ではどの演奏者も同じです。
ゆえに、その音響空間をうまく利用して演奏する事が、音程を正しく演奏する絶対的必要条件です。
例えば、分散和音はとても「良い関係」にある音の組み合わせ(倍音関係)ですので、「平均律」でもそのような音環境の中でうまく演奏すれば簡単に「純正律」に響いて整っていきます。しかしいつも整ってばかりでは変化のある表現にはなりません。時にはこの「良い関係」を破らなくてはならない場合もあります。
それが間違いなく出来るには知識が不可欠です。
その知識のなかでは、「調性感」はもっとも大切な物となります。
音楽はたくさんの種類の音程の音を出します。それらがそれぞれどんな関係にあるかが音楽の意味です。ただ無関係に並んでいるだけでは、意図を表現された音楽とはいえないでしょう。
確かに音楽の中では、どの音が頻繁に鳴らされるかで優劣が出来ます。また一番低い音にもそれを決める働きがありますし、大きな音も同様です。
作曲家はそれをうまく配置して、その優劣を作ってくれています。それが調性です
ですから、音をただ並べるだけの演奏でも、良い作品はそれなりにうまくいきます。
ただそれだけでは良く表現された演奏にならない理由は、理解されている場合は当然のようにその音楽の中の音の優劣や、より重要な音などが強調までいかなくても、落ち着いた十分豊かに響かす事が出来ますが、理解の無い場合は、むしろその重要な音がほかのあまり重要でない音に席を譲ってしまう可能性があります。
ましてや間違った理解をすれば、作曲家の意図とは違った表現にもなりかねません。それを自分自身の特別の解釈であるとは、不遜もいいところです。
その正しい理解のために、もいろいろな知識が必要なのです。
音楽をしている人たちは、ダイナミックと言えば、間違いなく「ff f mp mf p pp」 を思い浮かべるわけですが、単に音程同様「何処から何処までf」などとデジタル的表記と思うのは間違いでしょう。
それだけでなくこの表記を音響機器の音量数字と同様に考えてしまっていないでしょうか。
これらの表記は、あくまで表情をあらわす記号だと認識を改めてください。
では「音量」とは何なのでしょうか?
「音量」は、イントネーションの変化の要素としては、「量感」あるいは「質感」と言い変えられるのではないでしょうか。
後の D、音色 とも大きな関係が有りますが、あえて分けて説明しなければいけないのは、奏法上「音量」のコントロールのテクニックが「音色」のそれとは少し違うからです。
音量に関する言葉はずいぶん色々な物があります。「大きな音」「小さな音」はもちろん、「とおる音」「近鳴り」「やかましい音」「静かな音」「重い音」「軽い音」「しっかりした音」「頼りない音」「怒った音」「やさしい音」などあらゆる表現があります。
要するに「音質」と大いに関係が有ると言うことです。
テクニックとして、それを単に力の入れ具合でコントロールしているならば、最初の「大きな音」「小さな音」とだけの表現にしかしていない事に成るでしょう。
ガラスの割れたような大きい音は、一瞬の強い音です。鐘の音は、長い時間かかって減衰する音でしょう。
スピーカーのハウリングは、大きな鋭い音がずっと続く音です。緊急ブザーの音は、強い音が繰り返し鳴る音です。
我々にとって大きな音は、意外に体現できません。それは、そのような音がした時には耳をふさいだりして神経が防御します。
そのために自身で大きな音を出そうとすれば、自然に抑制したり、恥ずかしく思ったりで心理的にかなり制約を起こします。
もしもチャンスがあれば、タムタム(銅鑼)を思い切り叩かせてもらうのも良いでしょう。そのような抑制をある程度乗り越えることが出来ます。特に指揮者には有効な経験と思います。
小さい音については、そんなに説明は必要ないかと思います。
小さな音を出すにはそれなりのデリカシーが必要ですので、そのテクニックを磨くこと自体がいろいろな表情を体現していることになるでしょう。また音量の変化もそんなに大きな物にはならないでしょう。
注意したい点は、本当に小さくなりすぎないことでしょう。
もっとも小さい音は音を出さないことですから、それでは表現でも音楽でもありません。聞こえなければ、演奏していない事と同じです。
それだからこそ音質で表現方法を研究しなくては成らないのでしょう。
またその音量の変化も大きな問題です。
バロック時代、音量の変化は音楽の表現方法には無かったか、有ってもごく限られた物でした。
その当時の主な楽器はオルガンやチェンバロでした。音量の変化は自由にはとても無理でした。
ですから、音量が自由に変化できる楽器が登場したことは画期的な事で、だから音楽の大革命を起こしたのです。
それがピアノです。意外に最近の事です。たかだか二百年程前の事なのです。
すなわち、ベートーベンの頃からです。モーツアルトの頃はまだその段階にまで行っていません。
それも本当に自由に使えるようになったのは、19世紀四半世紀も経った頃、作曲家で言えばショパン、シューマン、リストあたりからでしょう。
もちろん、「crescend decrescend dim. >(アクセント)sf.」 など音量の変化が現れるのもそれ以後です。
言うまでも無いことですが、ある日突然始まったなどというものでは有りませんので、それ以前から徐々に現れていますが、その様な表現への欲求が高まっていたのでしょう。そこへ「p」も「f」も出る楽器「Pianoforute」つまりピアノが現れたのですからその普及は一気に進んだのでしょう。
J.S.Bachの頃には発明されて、彼が「このような物は使い物にはならない」と言ったそうですが、まだ時代の欲求が無かったのでしょう。きっと彼は、「音量の不安定な扱いにくい楽器」と思ったことでしょう。
そのことから、今使っている楽譜に音量記号があっても、その作曲家の年代や趣向から疑ってかかる必要が有ります。
もちろんその当時としては、音色も自由に作ったり変えたりする事は難しかったでしょう。
参考項目:音律、平均律、純正律、倍音、和声学、非和声音、フレーゼット
本来1つのフレーゼット(筆者はフレーズの最小の単位と言う意味でこの用語を使っています)は、1つの音が変化しているのだと書きました。すなわち1つの音は「a 始まり、b 伸びて、c 収まり」ます。(図、3)

図、3
この3箇所が、「イ、発音(a)」であり、「ロ、イントネーション(b)」であり、この「ハ、フレーズ(c)」で説明しようとしている所です。
通常の意味合いではもちろん、イントネーションにはこのフレーズの意味合いも含んでいるでしょう。音の表情も、イントネーションは先へ伸びているのに、フレーズは終るなんて事は有りませんから、密接な関係があります。
始まりは当然発音の問題です。やはり大きく関係してきます。
この終りの部分がフレーズを作ります。 <2、演奏とは?> の所で2つの音の例を出しましたが、その二つの音が繋がるか繋がらないかは、1つ目の音の終り方の表情にかかっているのです。
では、「どの様に終っているのでしょう?」
もちろん相対的で有る事には違い有りませんが、前の音が「次へ行こうとしているかどうか」が、大きな問題です。
終ってしまうのは簡単でしょう。しかし次の音はどの様にしても、それに繋げる事は難しいでしょう。
前の音が繋がろうとすれば、次の音はそれに答え受けとって繋がれば良いし、敢えてそれを無視して、違った出方も出来ます。「傘に架かった」ような、あるいは「かぶせる」ような、又は「ヒツコク繰り返す」様な表情など色々と考えられます。
それらは次の問題として、とにかくこの音は終っているのか、先へつながらなくてはならないのかが、ハッキリとしなければなりません。
たとえば、疑問の投げかけの時言葉では、語尾すなわち音の終りは上がるでしょう。音楽も当然疑問を呈するには、語尾は投げかける様に終ります。
言いかえれば、まだ先に何か有るように繋げようとするのです。
「答え」の時は、確信があれば落ち着いて行きます。語尾が「かな?」であればやはり投げかけます。
これは人間の基本的なフレーズ最後の音の表情でしょう。いかに多くの表情を作る事が出来るかを、認識して頂ければ結構です。
もう一点注意しなければならないのは、休符がある時です。
この休符と言う言葉が問題で、決して休みでは無くそこには音があって欲しくは無いと言う記号で、そこにはあらゆる意味がありますが、その点については又解釈で述べます。ただその時に、この音の終りの部分が大変重要に成って来ると言う事です。
声楽や管楽器では、「おじぎをしてしまう」等のまずい表情の形容もあります。なんとなく解かります。ただ音を止めるだけで、そこにフレーズの表情を意識しなければこの様に成ってしまいます。
その「音を止める」事は、すなわち「終る」という事です。
その最も頻繁に見られる誤りは、スタッカートが有る時です。スタッカートを、単純に「短く切って」と思っていては、この様に成ってもしかたが無いでしょう。
多くの場合軽い表現を要求されますので、これでは全く反対の重い表現にすら成ってしまいます。
重い表現を要求されるスタッカートも有りますので、その時にはこの様で正解です。一つ一つ終って、「足取り重く」すなわち先へ進みたくない表情ですから、正にその通りでしょう。
当然そのフレーズの意味する所を知って、それに合った処理が要求されるわけです。
「音の切れ」という言葉も使います。機械には最も難しい処理ではないでしょうか。我々人間のまだまだ存在価値のある所です。
打楽器やピアノの奏法としては、これは無理だとあきらめないで下さい。むしろそちらの方がより重要なのです。
それらの楽器では、発音した後は自然な音の減衰に任せてしまうしかありません。その減衰が上手く完全に消えてしまうのが終りのテクニックとすれば、まだ終らないうちに音を止めたり次の音が鳴ったりでフレーズを作るわけです。
最も考え無くては成らない部分でしょう。
「ピアノのダンパー(消音装置)の上げ方如何で、その奏者の力量が決まる」とまで言われています。
打楽器でも叩きっぱなしで無く、いかに止めるかの研究は怠れません。あまりそのような練習や指導は無い様ですが。むしろ何でもすぐに止めてしまう演奏を見かけた時には、せっかくの伸びやかな良い音を何故そんなにすぐ止めたいのか、大変疑問に思ってしまいます。
もちろん最も良い終り方は、自然の減衰のままなのですから、これらの人達は最も上手に音を終れるはずです。全く他の人達にとってはうらやましいかぎりです。
「どの様な音色でしょう?」と問われて、言葉で正確に表現するのは大変に難しいですが、凡そは説明できるでしょう。
何かに例えるか、この様な感じ、つまり音を聞いてこの様に感じたと言った感想で表現できます。
すなわち、常にそこに感情が伴っている事です。
感情の表現法なのです。
音楽の感情表現する事の出来る所はこの点以外には無いと言う事です。
楽しい音楽も、悲しい音楽も表現出来る事は、楽しい音色、悲しい音色を作るしかありません。
音楽は感情を表現するのですから、真にこの点は重要で有る事を、再度認識して頂きたく思います。
「ピアノはピアノ、フルートはフルート、ヴァイオリンは楽器(値段)次第、ましてや声は今更取り替える事は出来ない。」と、思うのですがその様な事ではないのです。
それぞれがそれらの特有の音色を有する事は、今述べ様とする以前の問題です。それは作曲家のオーケストレーションの仕事での話です。演奏法の前提、音楽の解釈としては有るでしょうが、それは後に述べます。
名ピアニストでも有る名指揮者W.サヴァリッシュ氏のリートのピアノ伴奏に対し、「鳥の声や、ホルンの音がした」と言われた事がありました。
これはどのような事なのでしょうか?
どの様な音を出そうかと考え、テクニックを駆使して、鳥の声やホルンの音を出したのでしょうか? それは疑問です。
多分そんな事はしてはいないでしょう。ただそのようなシュトゥエーションである認識は有った事は疑い無いと思います。
すなわち、彼はそのようなシュトゥエーションに忠実な音色をピアノで出そうとしたのでしょう。
それだけピアノでの音色の技術を持っていたと言えるでしょう。大変に優秀なピアニストであると言うより、大変に優秀な音楽家であるわけです。
指揮者であるからだと、その折にも解説者はその技術よりも指揮者の思考の為としましたが、それは単に彼が指揮者として名声が有る為だからでしょう。もう少し本質的な解説をして戴きたかったと思います。その為多くのピアニストは、自分たちとは無関係な事と思ったに違いないからです。
筆者もフルートを、故吉田雅夫氏に習った時に「フルートで色々な音色が出せなければ、これからはだめだよ」と、諭された事がありました。近年はこの様な事は、ほとんど聞かれなくなってしまった事は、残念に思っています。
それぞれの楽器特有の音を追及する姿勢が今の奏者の音色に対する唯一の興味である事は、考え直す必要があると思います。
では、「音色の違い」とは何なのでしょうか?
随分以前からは、音色の違いはその音の持っている「倍音」の違いであるとされていましたが、その後の音楽心理学の研究で、伸びている音の音色には殆ど違いは感じられなく、むしろ「発音」の時の「音の立ちあがり方」と「音の切れ方」の違いによるのだ、と解明されたようです。
我々音楽をしている者にとっては、それでも音の伸びている時にも音色感は在る訳ですから、まんざらこの結論を鵜呑みには出来ないと思っています。
それと、この様な音色感を、今追求しようとは思っていないという事です。
先ほどの、サヴァリッシュ氏の演奏のような表情としての音色感に、言及したいのです。
鳥はどの様に鳴くでしょうか?
決して「おずおず」とは鳴き出しません、突然静けさを破るように鳴き出します。リズムもテンポも前後の脈絡はありません。しかしそれぞれの種類によって一定の旋律を持っています。
特別な例は必要無いでしょう。ベートーヴェンの「田園」の中等に、たくさん例があります。
ドヴォルザークの交響曲第8番op.88
G-DurIの第2テーマが、最初フルートとクラリネットで鳥の声を提示し、それを次にヴァイオリンで人の声(歌)として感情を加えて出てきます。
その旋律のアウフタクトが、鳥は16分休符が挟まり、歌は付点8分音符でそれもクレッシェンドを伴う事で作曲家は意味合いの違いを見せています。(譜例、1)
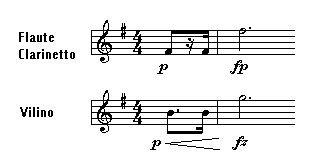
譜例、1 ドヴォルジャーク Sy.No.8 より
この読み方は後の<5.音楽の解釈>に譲るとして、この音符の違いには良い示唆が含まれていると思います。
すなわち、鳥を含め自然界の音には「はっきり」としか音は出ないと「発音」の項でも申し上げた様に、始めた後にクレッシェンド(音量の意味だけではなく)を伴うのは、非常に人間的感情表現だという事です。この部分の表情を「音色」と言っているわけです。
もちろん、このようにオーケストレーション、リズム、音量の変化のテクニックを使うのだと、結論づけるつもりはありません。
むしろその形を楽譜から読み取る事により、演奏家は何をするかが問題です。
これまで述べてきた音の始め方の「発音」伸び方の「イントネーション」「音量」の変化及び切り方の「フレーズ」等のテクニックを駆使した上で、音色を作る技術も必要であると説きたいのです。
もちろんそれぞれにその声や楽器によって限界はありますので、その中での事です。もちろんその幅が広いに越した事はありませんが。
声で使う「声色」もその一つですが、響きが壊れてしまっては、今までの論点が根底で変わってきます。そうは成りたくありません。しかし100歩譲って(本当は譲りたくはありませんが)その様な声も、シュトゥエーションに合っているのであれば良いと言えるでしょう。
しいて例えるなら、大砲や銃の音でしょうか。オペラの中でも時折実際に(もちろん本物では在りませんが)鳴らしますが、それからしばらくは全く音楽が耳に入ってきません。それでも必要かはその演奏家(指揮者や演出家)の、センスの問題でしょう。何か打楽器などで鳴らすように、スコアに記される場合もたくさん有ります。
このような音は例外として、音楽の中での音色の変化を考えた場合は、もっとデリケートな感情の変化として捉えて下さい。
この点がこの項の主題です。すなわち、感情の変化による音色です。
これこそ我々はいつも声でやっている事です。嬉しい時は「明るく輝いた」声ですし、悲しい時は「暗く沈んだ」声でしょう。優しい声でも、小さな子供には少し「軽い」あまり「深い響」ではない「しずかな」声で話しますが、恋人に話しかける優しい声は、少し「深く」「響き」の有る声でしょう。
このテクニックを使うのです。
特に声楽や管楽器では、本当にこのままのアンブシュアー(口の中や舌顎の状態)が応用できます。
ピアノや打楽器では、このような音色をイメージできる音を、タッチやマレットの交換で探すより無いと思います。それこそが練習なのですから。
このテクニックは多分に感覚のものだけに、それこそ才能だと言われてしまいそうですが、その音色を探す探求心と追及する熱意でしょう。そこに気が付く事が大切です。
むしろこの点の追求こそ一生続けなくては成らないし、良い演奏家ほど、この点への熱意が強いのかもしれません。
それが強ければ、間違った音など出せるわけが無いのですから、この点が名演奏家である秘訣かもしれません。
皆様の探求を応援します。
→ <4.演奏上の注意> ①テンポ ②リズム ③音程 ④音色 へ
<3.奏法の知識>
「演奏のマニュアル」のプリントアウトは、御希望者が多ければ考え様と思います。
B5(またはA4)で95ページほどに成りそうです。
もし御要望があれば御知らせ下さい。検討いたします。