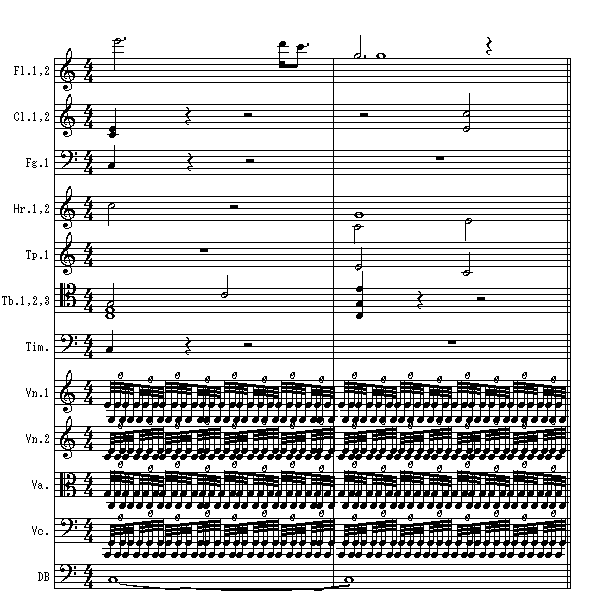
演 奏 の 解 析 法
−声紋分析(Sound Spectrogram)による解析−
英文目次用タイトル:Performance analysis by sound spectrogram
北 村 憲 昭
キー・ワード:音楽・演奏・分析・声紋分析
1.はじめに
まず始めに、このような音楽演奏を解析する事の必要性について述べてみたい。
私は指揮者であり、音楽家は演奏や作品を発表する事でその成果を世に問うのが本来の活動であると、音楽大学在籍当時から今まで何ら疑い無く演奏活動をしてきた。また他の音楽家達もその様に考えている。少なくともクラシック音楽家はその様に思っている。
また、音楽演奏の分析は科学的な計測で捉える方法になじまないと思うのが一般的であり、作曲家や作品、その楽譜の研究、音響学や音響心理学等、音楽演奏周辺の研究はずいぶん良くなされてはいる。しかしそれらは演奏の質の向上発展に貢献はしていない。その他の演奏家による演奏テクニックの著書もたくさん有るが、貴重な経験論も多く書き残されてはいるもののそれは演奏の内容表現方法までは言及されているものは少ない。はたして著書には記されてはいても、その事を理解するには多くの経験や知識それに音楽の素養がかなり有ればであり、それが解かればもうすでにその読者には十分な力があるのではないだろうか。それだけに演奏家自身はそのような演奏のテクニック(内容を現す為の)は一般には語ろうとはしない。
一つにはそこに踏み込む事こそがその演奏家の芸術性の本質に触れ、才能と言う神秘性を壊す物との考えがあるからに他ならない。
しかし音楽以外の芸術世界では、その様な考え方はかなり薄らいで来ている様に思える。音楽演奏にも科学的分析からのアプローチを考えても良い時代が来ているのではないだろうか。
一方昨今の音楽事情はずいぶん変化をして来ている。巷に氾濫する音楽は、ポピュラー音楽を中心にあらゆる音楽がTV、CD、などで提供され我々の日常の環境を支配している。その中で我々のクラシック音楽の分野は決して置き去りにされていると言う訳ではないと思う。ただマスコミや一般の人達の認識としては、才能に恵まれた一握りの人達の活動との賞賛(?)を含んだ言葉で表現されるが、実際には動物園の珍獣の様な存在としてしか扱われなくなっているように思われる。
そして当の演奏家は聴衆の賞賛の拍手を得るには、聴衆の興奮を呼び起こすような大向こうを張った演奏が有効であり、その手の内は演奏家の仲間内ではよく語られる。その一つ、終幕に向かってテンポをどんどん上げていく等の小細工は珍しい事ではない。そしてそれに興奮を呼び起こされた聴衆は、「感動的な演奏であった!」と、大いに拍手を送るのである。この様な事は今更の事では無く、かつての大指揮者フルトヴェングラーもその著書「音楽を語る」1) の中で、大いに嘆き、聴衆も演奏家共にもっと深い内容の音楽を求めなければ成らないと説いている。これが著されたのが1949年であるから、半世紀の間このような状況は続いてしまっているのだ。
それを何とかしなければなら無い時が来ていると思っている。
この神戸山手女子短期大学紀要NO.42に発表された長島洋一先生の論文「クラシック音楽とコンピュータ音楽」2)
の中でも、クラシック音楽家の活動やクラシックを学ぶ生徒に対しての疑問が語られている。それらの指摘に反論は無い。悲しいかな事実もあり、ゆえに一線の音楽家は努力を惜しまず、より良い音楽への追求を死ぬまで続けているのである。少なくとも良い音楽家達はそうしている。
この様な現状は、我々クラシック音楽家は何を考えどの様にして音楽活動を行っているのかを説明する機会を怠ってきたからではないかと、私は考えている。
すなわち、一般にはあらゆる社会の活動がこの様な論文で説明され紹介されている事実に我々演奏家が関心を持たなかった事を、深く反省しなければなら無いと思う。
もちろん今まで全くこの様な事がなされて来なかったのではなかった。あらゆる音楽の解説書や論説が有ったし、その様な著書は今でも書店には並んでいる。しかしながら多くの著書は演奏の当事者の弁で無く、愛好家や音楽専門家であっても作曲理論学者であったり音楽美学者のような著者が大半である。
私はかつてからその様な物でなく有名な演奏家の著書を捜し求め、ようやく出会ったのが、先ほどにも紹介した20世紀の名指揮者Wilhelm
Furtwanglerの著 "TON
und WORT" 3)であった。
しかしこの著も彼の名演奏の真髄が語られているものの、そこに具体的な彼の方法論は述べられている訳ではなかった。
もちろんその様な方法論は言葉で書き表す事は出来ないばかりで無く、とても多くの要素を含む事は想像に難くない。しかしむしろそのような理由で無く、その事こそが才能でありその演奏家個人特有の芸術的感性であり、その領域に迫る事こそ彼の偉大さを損なう事になる、との主張が一般的に成され来たからである。
しかし彼にも良い演奏をする理論が存在した。彼の伝記に登場する、Von
Heinrich Schenker の存在と彼の理論4)5)である。その事については今は触れないことにする。
またそれ以上に方法論の説明が難しいのは音の表現である。それに価値判断を下すのは個人の感性による方法しか存在しなかったからである。
ただ我々はその価値判断に疑問は抱いていない。むしろその価値が解る事がその音楽家の価値であり能力と思っているからである。しかしそれを証明する手段が存在しなかった。
そこでこの論文で、声紋分析法を用い客観的な科学の手法を用いた証明を試み様と考えたのである。
大変無謀な試みではあるが、先に述べた様に今の音楽の環境でクラシック音楽家の価値を認めて頂き演奏の技術を後世に伝えるには、この様な方法が不可欠と思う。
ただ決してクラシック以外の音楽分野を軽蔑するので無く、あくまで良い音楽を提供する者としての試みである事を御理解頂きたい。
2.音楽演奏の分析
音楽の分析は色々な分野に分ける事ができ、それがお互いに重要な関連を持ちその結果演奏として表現されるのである。
その中で今回私が取り上げようとするのは、音楽の最終部分である演奏された「音」その物を分析しようとする試みである。
近年目覚しく発達してきたのがコンピューターであり、音楽の分野もコンピューターで作られる音楽や演奏がいたる所で聞かれている。その音を聴くにつれ何か今までのアコーステイックな楽器に無い違和感が有る。
その最先端の技術者(Roland社)との意見交換をして見たが、最も印象的に平行線を感じたのが音程の問題であった。
音楽を勉強した者なら知っている用語で、平均律という言葉がある。一オクターブ(倍の振動数を持つ音の隔たりの事)を均等に12等分して作られた音律、つまりピアノやオルガンの音階である。
この音律で出来た音階の音は絶対的に正しいと、多くの音楽家を含め一般には誤って信じ込まれている様に思う。
音律の説明は他の書物に譲るが、自然界にはこの様な音の関係は無い。
その事をそれらの技術者は良く知っている。ゆえに、音のデジタル処理では細かな音の要素、つまり倍音をサンプリングで処理し、再現している。しかしいざ音楽や楽器を作る時にはその倍音の関係を無視した平均律を基本に作られている。この矛盾に疑問がある。
我々クラシック音楽家はこの問題をどの様に解決しているかを明かせば、ピアニストはタッチを変える事で音相互のバランスを取り、違和感の無い純正律の響が得られる事を経験的に知っている。その方法論は保科洋著「生きた音楽表現へのアプローチ −エネルギー思考に基づく演奏解釈法−」6)に詳しい。
声楽家はその様な純正律の音の関係でしか上手く声は響かせられない。ごく稀に非常に機用にそれぞれの音を平均律にあわせて歌う事の出きるテクニシャンは存在するが、その声楽家はあまり高く評価はされていない。その他の音楽家達、特にオーケストラのメンバー達は、理論的裏付けは別として、いつもとても注意を払っている。その問題に一番関心を持っていないのはオルガニストだけかもしれない。しかしオルガン製作者はバッハの時代から試行錯誤を続けているのである。
その研究から純正律に根ざした音程の関係や倍音の事は良く知られている。特にかつて音色はこの倍音の含み方で決められるとの理論が一般的であった。それは事実で無い事はすでに証明されているが、音色の大切な要素である事には間違い無い。
その音程や音色が演奏家の最も関心事なのである。
これらのリアルタイムの解析が今こそできると考えている。そのツールが声紋分析法である。
もう一点大切な目的が有る。
音のイントネーションである。一般に言葉の世界では普通に使われているが、イントネーションという用語は余り日本の音楽の世界では使われない。日本で「速い、遅い」「強い、弱い」「高い、低い」「アクセントを付けて、付けないで」等の言葉で注意を促す時に、西欧では一言で「イントネーションが違う」という一言での注意を耳にする。私もヨーロッパでのオーケストラの練習の時は便利に使っている。
日本人の一般的思考として物事を詳細に分析しようとする傾向がこのような言葉での説明に現れているのであろうが、それで全てを説明できれば良いが中々難しい。あいまいなイントネーションと言う言葉に含まれた要素を検証しなければならない。
イントネーションにはテンポの変化が含まれ、その視点での研究はされている。最近の書で渡辺裕著の「西洋音楽演奏史論序説」7)ではベートーヴェンのピアノソナタの研究でずいぶん詳細に成されている所である。しかし、音楽の表現としてはむしろ音程と音色の変化に関しての響のニュアンスに大いに注目しなければならない。しかし其処までは踏み込めないで来たのが現実である。
それは前に紹介の、保科洋著「生きた音楽表現へのアプローチ」6)でも、著者が「このような演奏者個人の感性に委ねられている表現法についてはひとまず置いておき、……」(P.51)と前置きしている所なのである。
しかしこの部分を避けては音楽演奏の良し悪しは語れない。むしろ「1.はじめに」で述べた、我々の演奏の価値基準は実はそこに有るのである。今までは客観的な証明の難しかった所だ。
これらを一目で見る事ができるのがこの声紋分析なのである。
3.声紋分析(Sound Spectrogram)について
声紋分析とはサウンド・スペクトログラム(Sound
Spectrogram)8)9)、すなわち音声の周波数スペクトルの時間的変化を図形で示した物で、最近セキュリティーシステムの一つとして、声の特徴からその人物を特定するのに使われるなど、かつてから広く知られてきた物である。
その様に人の声を分析する為に開発された物だ。すなわち声と言う音を数字に置き換えそれをグラフにして表した物である。
すなわち音の要素である ピッチ、強さ、時間、を視覚化した物で、この要素は音楽の要素と何ら変わりは無い。まったくと言っても良いほどに音楽の要素である。ただ違うのは、視点がその空間に存在する音の全てを扱う事と、その時の音の主要な成分の音を扱う違いである。
しかし実際の音楽演奏ではその時の全ての音が問題である。ゆえにこの声紋分析の取り扱っている要素は、実は音楽演奏の大切な表現の部分であると言える。
具体的な要素を述べるなら、第一に音が必ず持っている倍音の要素である。ここでは倍音の説明は省くが、どのような音にも含まれ音色を決定する大きな要素である事は前にも述べた通りである。
音楽で扱う音は通常「楽音」と言われ、雑音を含む音は騒音として極力避けたい音のように説明され扱う事さえはばかれてきたのだが、実際に音楽心理の実験で音色の決定にはこの雑音の含まれ方や発音時の雑音でその音色が決定されていると言った結果もあるように、やはり音楽の演奏では欠くべからざる物と言える。言葉を変えて言うならば、楽音として取り扱う音すなわち楽譜に記された音以外の音も演奏上大切な音といえる。
これらを忠実に、あからさまと言えるほどに白日の下にさらけ出しているのが声紋分析であろう。それゆえに演奏家にとって秘密にしておきたい感情は理解できる。それを敢えて試み様と思う。
もう一点が先ほど述べたイントネーションだ。
これもやはり楽譜上には書かれてはいない。「> ・ cresc. dim.」等のように表情を示す記号が有るように思われているだろうが、これらはあまりに大雑把でヒント程度でしかない。ゆえに楽譜からその部分のイントネーションを読み取る事が求められる。それが解釈と言った用語が使われる所以だ。
そしてそこに神秘性や閃きの才能を求められるのだが、普通一般の人達が文章を読む時に「行間を読む」様に音楽家は楽譜を読めるのであり、そこには文章の解釈と同じく大きな解釈の相違はあまり無い。無いはずであるが、楽譜を文字の様に読める能力開発研究は今一歩文学の様には行っていないのが現状であり、そこが音楽演奏の向上発展を阻む原因ではないかと思う。
その議論はまたの機会に譲るが、この声紋分析が解決に寄与できるかもしれない。
このイントネーションは、刻々の響すなわち音色の変化こそその表現であるので、倍音の含み方に大きな変化が現れるのではないかと見ている。それをこの声紋分析では一目で見て取る事ができる。
そしてこのイントネーションの取り方によって音程すら変わってしまうのである。その説明はなかなか複雑で前述の平均率と純正調の問題と共に考えなくては成らない問題であるが、それらを見る事もできる。
本論文における声紋分析は、パーソナル・コンピューター(Windows98)と、フリーソフトとして提供された次のWindows用アプリケーションを使用した。
声紋表示変換ツール「声門」Ver.0.97
2001/4/7(c)1998-2001 T. Tokairin
URL :
http://www.fides.dti.ne.jp/~tokai
分析の方法は、音のサンプルを
Windows 形式音声 WAVE ファイル(*.wav) に変換してから、このソフトで「声紋」画像を作成表示、保存する様に成っている。この作業は大変に簡単な物で、実際にはこのソフトを起動し、
WAVEファイルを開くだけで声紋の画像が表示されるシステムである。声紋ウィンドウは、縦軸は周波数(
0-20000Hz)、横軸は時間となり、色の明るさ 赤 → 黄色 → 緑 → 青 → 黒 の順にその成分の強さを示している。この論文の図はモノトーンであるので色の濃さで表されている。(掲載の図は、本来のカラーからモノトーンで印刷した物である。)本来の図は筆者の
HP18)を参照されたい。
4.演奏の声紋分析例
以上の事を踏まえ、具体的な演奏の解析の例を挙げる。
解析の対象に選んだのは、ブラームス作曲 交響曲第1番 第4楽章より、序奏に続くホルンで始まるテーマのフルートによる最提示部の最初の1節 第
38―39小節(楽譜1、参照)である。このテーマは1868年ブラームスがプラトニックに思いを寄せていた、師ロベルト・シューマンの妻であり天才ピアニストと言われたクララ・シューマンの誕生日に送った歌の旋律である。
この部分を解析の対象に選んだ理由、
分析手順
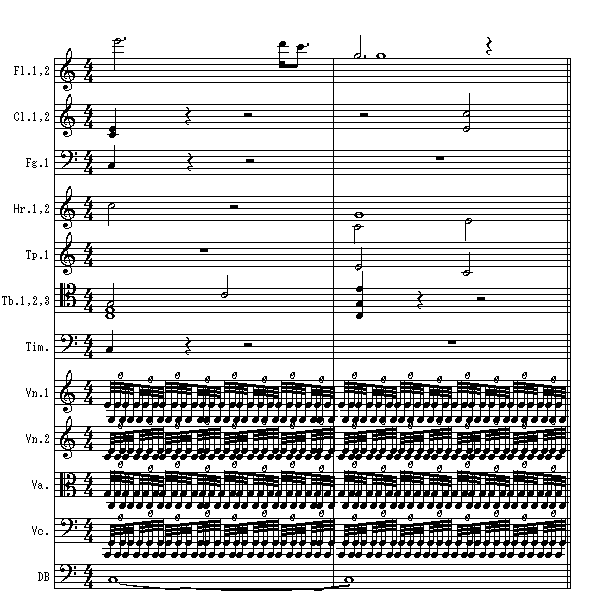
楽譜
1、Johannes BRAHMS Symphony No. 1 c-moll op. 68 第4楽章より第38―39小節
4.1. MIDIで作成した演奏の声紋分析。
A. 分析の結果
この音源で注意すべき事は、
・MIDIシンセサイザーは全くの平均律による音程で出来ている事。
・コンピューター内での合成で作られた再生音である事。ゆえに生の音は介在していない。
制作手順は、楽譜制作ソフトEncoreでMIDI音源制作 → wave変換 → 声紋分析
(全てコンピューター内での変換)
図1、に結果を示す。
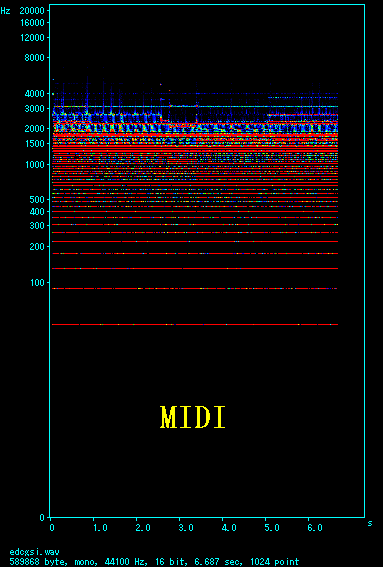
図
1、MIDIで作成した演奏の声紋
B. 考察
4.2. 四種のオーケストラによる演奏から採取した声紋分析。
A. 分析の結果
この4種の演奏は、かねてから名演奏といわれている物であり、それぞれの指揮者やオーケストラはもとより、フルーティスト(第4の演奏は不明)も共に名演奏家と言われる人達である。
録音年代に幅があり録音された環境なども全く違うので、その優劣は考えないことにする。
第4番目の演奏だけが基本ピッチが、A=440Hz で低く聞こえる。
しかし4.1.のコンピュータと同じA=440Hz ピッチである。
他は A=442Hzと思われる。
制作手順は、CD → WAVE変換 → 声紋分析
第1の演奏:10)
ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ウイーン・フィルハーモニー
(Fl. ハンス・レツニチェック )1948録音
第2の演奏:11)
シャルル・ミュンシュ指揮 パリ管弦楽団
(Fl. ミッシェル・デボスト) 8-12 Feb. 1968録音
第3の演奏:12)
カール・ベーム指揮 ベルリンフィルハーモニー
(Fl. カール・ハインツ・ツェラー)1960録音
第4の演奏:13)
カール・マリア・ジュリーニ指揮 ロスアンジェルス・フィルハーモニー
(Fl. 不明)Nov. 1981録音
図2、に結果を示す。
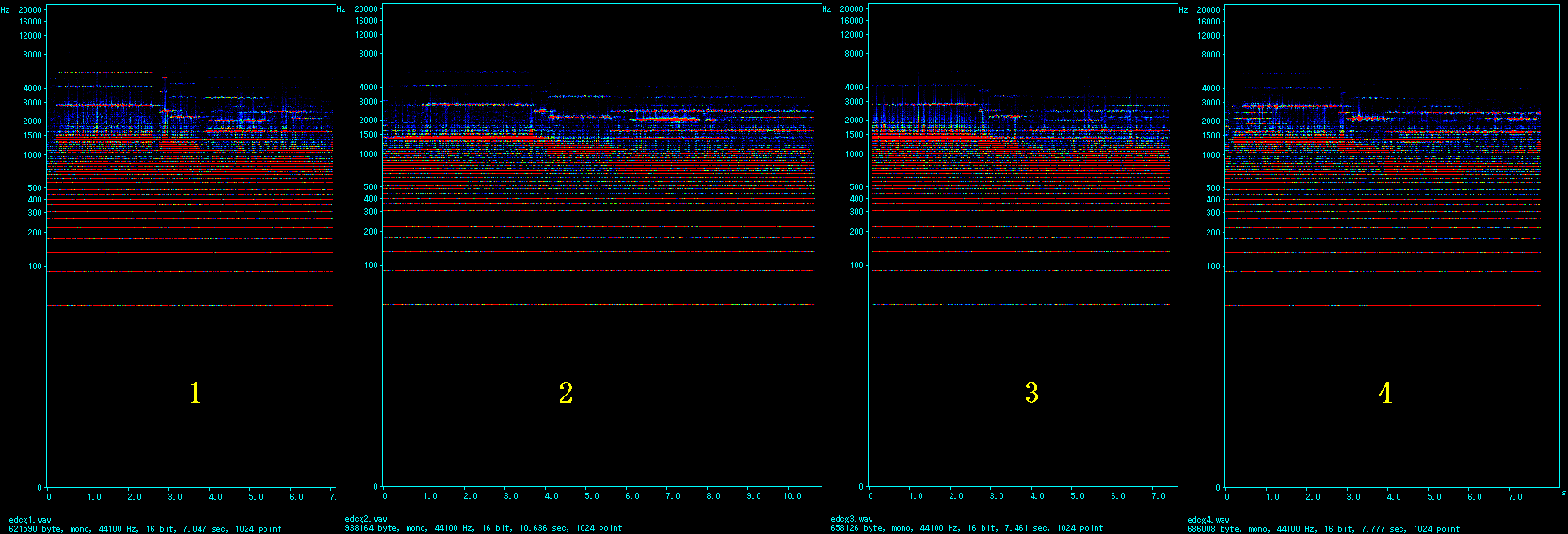
図
2、四種のオーケストラによる演奏から採取した声紋。B. 考察
4.3. 旋律と伴奏の音の重なり合いの関係をMIDI音源で分析を行う。
以上の分析では、このような分析はむしろフルート奏者に関しての問題であり、指揮者や伴奏の演奏が大きな意味をもたないと考えられる事が一般的であろう。しかし旋律の音は伴奏によってかなり変化する。
その旋律と伴奏の音の重なり合いの関係を説明するMIDI音源の分析を行う。
A. 分析の結果
注)この資料の演奏は、音の重なり合いの資料なのでリズムを変形させている。
最初に旋律だけの演奏、重なったC音、CG音、CE音、CEG音の伴奏のみ、C音の伴奏と旋律、CG音の伴奏と旋律、CE音の伴奏と旋律、CEG音の伴奏と旋律、この順にMIDIで製作した物を直接声紋にかけた。(下段の楽譜参照))
この音源で注意すべき事は、
・ MIDIシンセサイザーは全くの平均律による音程で出来ている事。
・ コンピューター内での合成で作られた再生音である事。ゆえに生の音は介在していない。
制作手順は、楽譜制作ソフトEncoreでMIDI音源制作 → wave変換 → 声紋分析
(全てコンピューター内での変換)
図3、に楽譜と声紋を対比させて示す。
|
|
図
3、旋律と伴奏との音の重なり合い(MIDI音源)の声紋B. 考察
以上の事から、伴奏と旋律の関係は想像以上に大きい事が判る。
オペラの現場などで良く言われている事だが、歌手は自分の声が消されてしまうのでオーケストラはなるだけ抑えてくれとの要求をするが、実はどの様な場合でも決して伴奏が旋律を消す事は無く、むしろ声に厚みを加え音量をフォローする働きがある事は、指揮者はよく知っている。
この声紋はそれを実証してくれている。
しかし反対に、伴奏にE音が鳴った時に旋律のE音の輝き(倍音)が無くなった事実から、純粋倍音で無い音、すなわち純正律でない音であればその旋律音を消す事も有りうる事の証明にもなるだろう。
生かすも殺すも伴奏しだいと言ってもさしつかえないのではないだろうが、soloの音程が伴奏と違っていても同じ結果になる。
オペラの現場で、歌手の要求にしたがって伴奏の音量を極端に抑えた時にむしろソロの声が響かなくなった経験は何度もある。
この事から伴奏も旋律も全体には大いに影響しあっているのが判るだけでなく、お互いがその影響を知らなくてはお互いが邪魔をし合う事の実証になるだろう。
アンサンブルの重要性は今更述べるのもはばかられる事ではあるが、精神的理由や音楽の繋がり、モチーフの対比、ハーモニーの構築などの問題だけでなく、実際の音の響き方に大いに関係する事が証明されたのではないだろうか。
この分析資料は全くの機械での音源であり、コンピューター内での処理であるので、我々の実際の演奏とは違うが、機械的な正確さが至上の物とする発想がいかに良くないかは間違いなく見て取れると思う。
4.4.総合的な考察
MIDI音源や四種CD音源それぞれの声紋のあまりの違いに、むしろ戸惑いを覚えている。
最初はMIDIの結果と比較する事でその違いが現われるとの予測から始めたが、これだけの違いが見て取れるとは思わなかった。
誤算では有るが、この声紋による分析方法がこれからの演奏の解析にいかに役立つか、確信を持つことが出来た。
フルートの旋律の周波数はおおよそ700Hz〜1300Hzであるので、その付近の赤くハッキリとしたラインが実音であり、それより上の音は楽譜上には無いので全て倍音である。
この分析例ではFl.が一番高い音域でありその旋律線がハッキリしているので、その進行と共に倍音が変化している事がハッキリと出ているので良く判る結果となった。これが内声や低音の旋律線であれば少し判り難い結果になったと思われる。
この結果から大きな意味での読み取れる事としては、演奏者が(指揮者も含めて)どの様な姿勢で演奏に望んでいるのかが明らかになった。
すなわち私も演奏家であるので良く判るのだが、なにより第一に気を配る事は良い音を出す事であり、かなりの精力をそこにつぎ込んでいる。それはどんな音楽家でも変わらないと思う。
その一瞬に全体の響や曲の構成流れなどを判断し、前後の抑揚から今の最善の音を作り出す作業を繰り返しているのであり、そこに作品への思索の深さが判断の拠り所と成り、その音楽家の質が現れるのである。筆者のホームページ17)でそのような良い音や良い演奏の考察を進めている所である。
これらの結果からもその様子はずいぶんハッキリと見る事が出来た。しかし、良い音の基準からだけで見ればMIDIの演奏は決して悪い見本ではないはずであるが、実際の音楽的な響として見れば良い演奏とは程遠い結果である。その要因をこの声紋から見出すとすれば、やはり「流れ」の違いであろう。
すなわちイントネーションである。
どの様な演奏でも人が演奏する以上言葉通りの機械的演奏は出来ない。そこには何らかの抑揚を伴ってしまう。そこに色々な意図を見る事が出来るのだ。
外国語の習得の折に良く有る事だが、同じ抑揚のつもりであってもネイティヴの抑揚(発音)とはかなり違っている事に気が付かない事がある。そのような教育にこの声紋が使われているといった話も聞くが、確かに有用で有る事はこの分析からも明らかである。
まして音楽の教育に生かせない事は無いと思う。
言葉以上に音楽にとってこのイントネーションの問題は、抽象的概念でも有り、ただ口移しの様に先生から生徒に受け繋がれてきた点である。その最も顕著な例が邦楽の伝承であるのだが、世界中の音楽教育全てにも同じ方法論が取られてきた。
そこに一石を投じる事が出来、素晴らしい音楽の演奏を多くの人達に伝承できる事になればこれに勝る喜びは無い。
5.終りに
まだこの様な分析を始めた所であり、もっと詳細な分析や多くの資料による検討をしなければならないことは言うまでのない事であり、この分析からももっとたくさんの情報が得られるであろう事も想像に難くない。
この様な試みで今までの名演奏の真髄にどこまでせまる事が出来るかは、むしろこれからの問題となるが、今までには研究者の感性で述べられてきた演奏論に、大いに裏付けを与えるものに成る事に違いないと思う。
勿論この声紋を分析するには、音響学や音響心理からのアプローチも欠かせない事であり、それら研究者の研究手法の一環と成る事を望むものである。
また音楽演奏の教育に携わる者にとっても、過去の言い伝えや対処療法的指導で無く、明らかな良い演奏の指針を求める事も可能ではないかと思うのである。
これらの事によりこの声紋分析による演奏の解析は、良い音楽家達の持つ価値基準を一般の物とし、音楽の質を高める事に貢献できる物である事を信じている。
勿論クラシック音楽の分野だけで無く、コンピュータ音楽を始めあらゆる音楽の演奏に応用されれば、世の中に氾濫する音楽がもっと好ましい物に成るであろうと思う。
この様に視覚に訴える形で演奏を見る事は、その分析もさる事ながら、良い演奏は一見して美しく整っている事であり、それぞれの演奏の特徴がこの色彩からも感じる事は大きな特徴と言えるのではないだろうか。
また、これほどに演奏によっての相違がハッキリと見て取れる事は、これから演奏の解析が容易に行う事が出来、かつての名演奏の研究に大きな発展を見る事が出来ると確信を持つ事が出来た。これからは個人の演奏にもこの声紋で分析を試みるつもりであるが、良い演奏ほど視覚的にも美しいのではないかと楽しみすら覚えている所である。
しかしこれらの声紋分析例だけでその点の優劣はつけがたい。それは、それぞれがオーストリア(ウイーン)、フランス、ドイツ、アメリカ、を代表するオーケストラであり、高い評価を受けているだけで無く、その国の特徴をハッキリ持っているからだ。
あいまいな?中間色的な赤や緑を好むオーストリア、カラフルな色彩のフランス、ハッキリとした色彩のドイツ、一見無造作?な色合いのアメリカ、まさに音色もこの声紋の様である。是非カラーの声紋図を見ていただきたいものである。(筆者のホームページ18)に掲載されている。)
しかし、これらの声紋は音の分析結果であり、この色調は音量の分析で音色が対象では無いのだが、国民の行動様式の嗜好がこのような結果に出るのだろう。やはり視覚的な評価も判断の一つに成るだろう。
その点からもやはり最も良い演奏はフルトヴェングラー指揮ウイーンフィルハーモニーの第1の演奏だ。全体的に統一感があり良い響きと言える。
全体の倍音の分布が他の物に比べて均一である事、この1節だけでは確定はし難いが常に同じ響を保っている。フルートが他の演奏の様に響が突出していないのも、全体として見れば整った響になっていることに繋がっている。その為に、音色がまろやかで優しく響き、暖かい豊かな包容力の有る音色になっている。
この様な特徴は元来ウイーンフィルの特徴でもあり、フルトヴェングラーの音楽の評価でも有るわけで、この二者によってこの様な名演奏が生まれたのであり、それをこの声紋はハッキリと見せてくれている。
本来音の評価はその演奏を聴いてこそ判断が出来、評価されるものである事は最初にも述べた。この様なグラフでは本来の良さは十分に図り得ないので、実際に聴けばなおこの声紋で見られる特徴が理解されると思う。
これらの音源10)11)12)13)は、容易に手に入るCDなので、是非1度実際に聴かれる事をお勧めする。
筆者のホームページ14)ではこれらの声紋をカラーの大きなサイズで掲載しているので、そちらも参照していただきたい。
参考文献
1)フルトヴェングラー・ウィルヘルム、『音楽を語る』門馬直美訳、創元社、1952。(Furtwangler Wilhelm, Gesprach uber Musik. Atlantis Verlag Zurich, 1949)
2)長島洋一「クラシック音楽とコンピュータ音楽」『神戸山手女子短期大学紀要』第42号(1999)、p.27−45。
3)フルトヴェングラー・ウィルヘルム、『音楽と言葉』芳賀檀訳、新潮社、1981。
(Furtwangler Wilhelm, TON und WORT'. 1954)
4) Schenker Heinrich, MUSIKALISCHE THEORIEN UND PHANTASIEN VOL. 3 DER FREIE SATZ. UNIVERSAL EDITION, 1935.
5)シェンカー・ハインリッヒ、『ベートーヴェン第5交響曲の分析』野口剛夫訳、音楽の友社、 2000。(Schenker Heinrich, BEETHOVEN FUNFTE SINFONIE. UNIVERSAL EDITION, 1923.)
6)保科洋、『生きた音楽表現へのアプローチ』音楽の友社、1998。
7)渡辺裕、『西洋音楽演奏史論序説』春秋社、2001。
8)阪上公博他、『音のなんでも小事典』日本音響学会、講談社、1996。
9)古井貞熙、『音響・音声工学』近代科学社、1992。
10)Brahms J. Symphony No.1 c-moll op.68. Wilhelm Furtwangler, cond. Wiener Philharmoniker, Rec. 1948, EMI Records Ltd. CDZ 25 2322 2 (CD), 1989.
11)Brahms J. Symphony No.1 c-moll op.68. Charles Munch, cond. Orchestra de Paris, Rec.8-12 Feb. 1968, 東芝EMI株式会社, CC33-3417 (CD), 1987.
12)Brahms J. Symphony No.1 c-moll op.68. Karl Bohm, cond. Berliner Philharmoniker, Rec. 1960, Deutsche Grammophon BELART, 450 107-2 (CD).
13)Brahms J. Symphony No.1 c-moll op.68. Carlo Maria Giulini, cond. Los Angeles Philharmonic Orchestra, Rec. Nov. 1981, Deutsche Grammophon Polydor International, 427 804-2 (CD), 1982.
14)http://homepage1.nifty.com/nma-yc/
15)http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/7129/
16)http://homepage1.nifty.com/nma-yc/sidouhou/mokuji.htm
17)http://homepage1.nifty.com/nma-yc/meiennsou/index.htm
18)http://homepage1.nifty.com/nma-yc/meiennsou/siryou2/brahmus.htm